
毎月、猿が仲間に「ここにバナナがあるぞー」と知らせるみたいな感じに、英語で書かれた本について書きます。新刊には限定せず、とにかくまだ翻訳のない、面白い本を紹介できればと。
で、その第1回。今年出たZorrieという小説について書きます。
「ゾリー」とはヒロインの名前。160ページ程度の、長篇というよりは中篇の長さで、ゾリー・アンダーウッドという女性の生涯が綴られる。その書き出しは——
この冒頭からわかるとおり、ゾリーは仕事の効用を信じる人物である。体が言うことを聞かなくなって、休憩が必要になっても、休憩まで一種の仕事のように捉えている。これまでずっと、働くこと、体を動かすことで、問題を解決できないにしても問題を腕一本向こうに追いやっておけると信じ、事実たいていの場合はそうしてきた人物なのである。
こういう人は普通、小説の主人公にはならない。なるとしたら、最初はこういう地味なところから出発しても、やがて何か劇的なことが起きて、性格にも劇的な変化が生じたり立場が劇的に変わったりして主人公の資格を得る。でも先回りして言ってしまうと、ゾリーにそういう変化は起こらない。現在のゾリーを描いたこの第一段落のあと、時間はゾリーの幼いころに戻って、以後その生涯がたどられるが、そのなかで彼女はあくまで「普通の人」でありつづける。
むろん印象的なエピソードはいくつもある。たとえば、ゾリーは一時期、オタワの時計工場に勤めて、時計の文字盤に夜光塗料を塗る仕事に従事する。夜光塗料にはラジウムが入っていて、工場で働く女の子たちは筆先を整えるのに舌を使うよう言われ、さらには化粧品代わりに塗料を顔や爪に塗るので、彼女たちが夜に街を歩くとその身が光る。それで人々からは「ゴースト・ガール」と呼ばれる。これは史実に基づく話であり(オタワにまさにそういう工場があった)、現実には多くの女性が放射線中毒となり、「ラジウム・ガールズ」と呼ばれて大規模な訴訟問題にも発展したわけだが、ゾリーもその後流産した際に、かつて摂取したラジウムの影響ではないかと考える。だがその因果関係は曖昧なままで、ドラマに発展することない。これによって彼女が大きく変わったり、世界との関係が大きく変化したりすることはない。彼女は依然として働き者の普通人である。そういう人物が、短めの長篇とはいえヒロインだというのは、けっこう珍しいことではなかろうか。
ヒロインのファーストネームが題名になっている小説はほかにもある。ウラジーミル・ナボコフの『ロリータ』、トニ・モリソンの『スーラ』、スティーヴン・キングの『キャリー』……だがこれらの小説のヒロインは、みんなもっとずっと際立った存在である。ロリータは妖婦的少女(と、男が見るだけなのだが)だし、スーラは共同体の調和をかき乱す奔放な人物、キャリーはおよそパッとしない少女だが苛められたことで彼女の中の暴力性が爆発し……みんな何らかの意味で、周りから浮き上がっているか、浮き上がるに至るかする。だがゾリーはそうではない。その意味で、彼女は、あるいはこの小説は、地味に異色である。
そもそも、たかだか160ページの小説で人の一生を綴る、というのは、19世紀の小説ならいざ知らず、現代ではめったにやらない書き方ではないか。たとえば、子供のころをフラッシュバック的に参照しつつ、大人になってからのある危機的な一時期に焦点を当てる、といった書き方の方がはるかに一般的だろう。その意味でも『ゾリー』は、地味に異色である。
そして、その文章。すでに引いた冒頭からある程度おわかりいただけると思うが、コツコツ仕事することの価値を信じるヒロインの心性を反映するかのように、文章も淡々としてオーソドックスである。ほとんど事務的と言っていいような律儀さが、そこには感じられる。
で、レアード・ハントがいつもこういう文章を書いているかというと、まったくそうではないのである。作品ごとに当然トーンも変わるので単純化は禁物だが、個人的には、一番この人らしいのは、あまり教育を受けていない、素朴な喋り方をする語り手に不思議と詩的な表現をさせて、それがなぜかリアルに響く、というような書き方だと思う。「むかしわたしは鬼たちの住む場所にくらしていた。わたしも鬼のひとりだった」(“Once I lived in a place where demons dwelled. I was one of them”)という、『優しい鬼』本篇の書き出しなどはその典型だろう。『ゾリー』の文章は、それとはまったく違う。

訳=柴田元幸/朝日新聞出版
というわけでこの小説、現代小説全体から見ても、レアード・ハント作品群との関係から見ても、一見個性的でないことによって、非常に静かに個性的なのである。おそらくレアード・ハント作品のなかで一番読みやすいと思うが、その読みやすさは英語でよく言うdeceptively simple(簡単に見えるが奥は深い)というやつで、実はほかのどのハント作品よりも多くを読者に要求しているかもしれない。読者はつねに行間を読みとるよう求められ、その努力は十分以上に報われる。特に、再読で味わいは増す—— たとえば、すでに引用した冒頭でも、再読する読者は、「両手をぎゅっと脇腹に押しつけ」るしぐさをこの小説でほかに誰がするかを知っているし、「ステンドグラスのカケス」をゾリーが誰からもらったかも知っている。
この静かな個性にモデルがあることは、指摘しておかないといけない。作者自身によればこの作品は、エピグラフにも使っている、フロベールのTrois contes(三つの物語)の中の“Un cœur simple”(邦題「素朴なひと」「純情な女」など)の構造を踏まえている。で、「素朴なひと」を読んでみると、たしかに構造は似ている。だが「素朴なひと」のフェリシテは19世紀フランスの身分社会を生きる召使いであり、20世紀戦後のアメリカ中西部で農場を所有して生きるゾリーとでは、行動の自由度、宗教観、世界に関する知識などは全然違う。結局のところ、両者の最大の共通項は、どちらも普通の人への敬意に満ちた素晴らしい作品であり、「普通」がいかに豊かかを静かに謳い上げているということに尽きる。
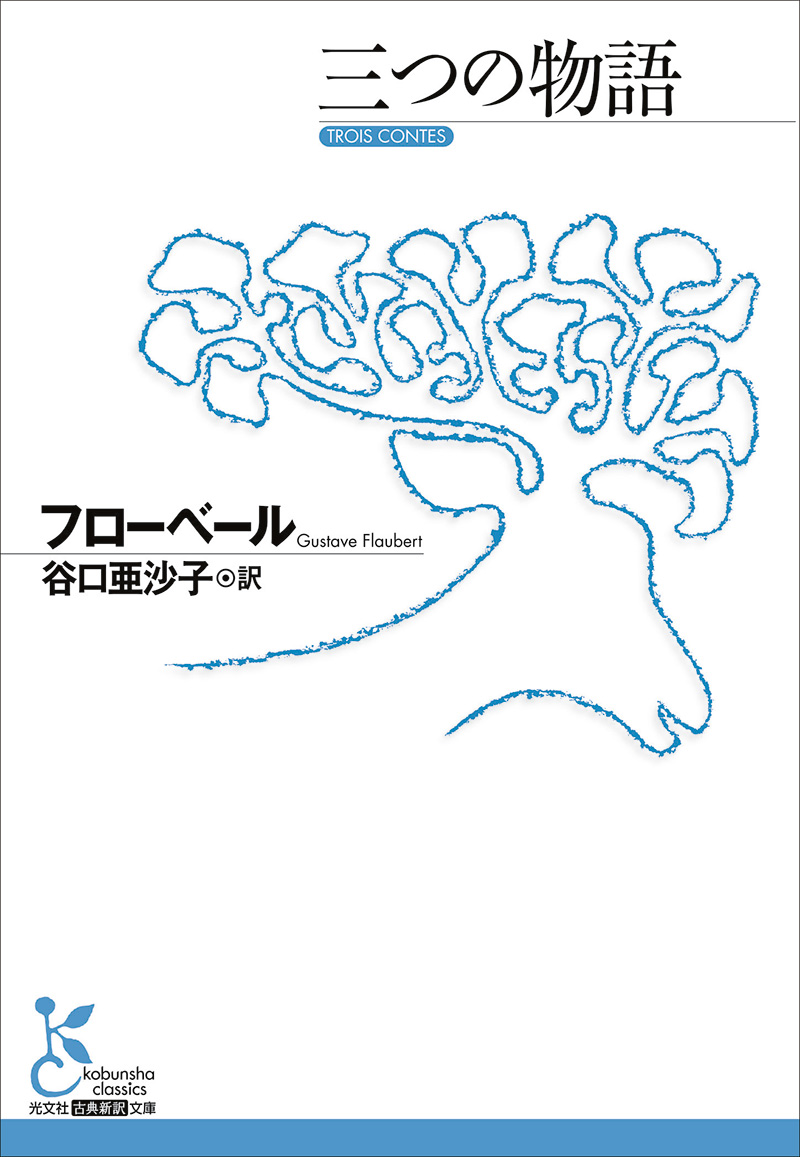
訳=谷口亜沙子/光文社古典新訳文庫
まずは『ゾリー』の静かな異色さを強調したが、とはいえこの小説が、いままでのハント作品とまったくつながっていないかというと、それもまた違うのである。ハントの第2作『インディアナ、インディアナ』のなかに、実はゾリー・アンダーウッドという女性がほんの少しだけ登場する。

訳=柴田元幸/朝日新聞出版
舞台は1950年代のインディアナ(つまり、『ゾリー』と同じ)。主人公のノアは、妻の(厳密には結婚していない)オーパルと離ればなれに暮らしている。精神に問題を抱えたオーパルが自宅に火を点けて病院に入れられ、オーパルが過度に興奮するからという名目で、やはり精神にいくらか問題があるノアは、面会すら許されていない。
そうした事態に耐えられなくなったノアは、自分も病院に入れればと、これまた自宅の納屋に火を点ける。だがその「計算」は正気の証拠とされ、事はノアの思いどおりには運ばない。ゾリー・アンダーウッドは、そんなノアのもとに、毎日食事を届ける役割を買って出る。二週間にわたって食事を届けつづけた末に、ゾリーはノアへの思いを告白しかけるが、依然オーパルを愛しているノアは、その気持ちに応えることはできない。
ゾリーはそれっきり小説から姿を消す(それ以前には一度だけ、チェリーパイを届けてくれた人物として、ノアがオーパルに宛てた手紙の中に登場する。ゾリーが作ったパイをノアは「そんなに大したパイじゃなかった」と評している)。読者のそれなりの同情をしばし得はするかもしれないが、おそらくは大半の読者がじきに忘れてしまうであろう脇役的人物。
その女性、ゾリー・アンダーウッドに、焦点を当てたのが、今年出たハントの新作というわけである。そして今度の小説でも、ノアは主要な人物の一人であり、放火のエピソードをはじめ、いくつかの出来事は両作でオーバーラップしている。『インディアナ、インディアナ』を読んでいなければ『ゾリー』がわからない、ということはまったくないが、両方読めば、両者の語り口の違い、それを超えた共通性(たとえば、これはもう小説的技巧というより人徳としか思えない、作品全体から伝わってくる、登場人物に対する作者の優しい目)が見えて興味深いと思う。
そしてまた、作者本人が書店トークで語ったところによれば、『ゾリー』の起源はもっと以前までさかのぼる。31年前、埼玉県熊谷市で英語教師をしていたときに書いた(そして初めて自分でも手応えを感じた)“Old Woman”と題した短篇小説に端を発しているという。そういう意味で『ゾリー』は、作家としての出発点に戻った作品とも言えるかもしれない。20世紀なかば、アメリカ中西部を舞台とする物語が、まず日本の一都市においてその萌芽が現われたと思うと、なんとなく嬉しくなる。“Old Woman”の冒頭、主人公の女性はまず、ジャガイモの皮を剝いているという。
最新情報
〈刊行〉
研究社刊、『英文精読教室』第1巻「物語を楽しむ」、第2巻「他人になってみる」発売中。
アルク刊、『対訳 英語版でよむ日本の憲法』(2015年刊『現代語訳でよむ 日本の憲法』増補改訂版)発売中。
〈イベント〉
5月19日(水)19時- 『英文精読教室』刊行記念オンラインイベント(ジュンク堂池袋本店主催)。
5月29日(土)14時- 手紙社主催毎月恒例オンライン朗読会「いま、これ訳してます part 13」
〈その他〉
バリー・ユアグロー超短篇「旅のなごり」手書き拙訳稿を包装紙にしたサンドイッチを、三軒茶屋のカフェnicolasで販売中。
朝日新聞金曜夕刊にジョナサン・スウィフト『ガリバー旅行記』新訳連載中。
MONKEY23号「ここにいいものがある」
(岸本佐知子・柴田元幸短篇競訳)発売中
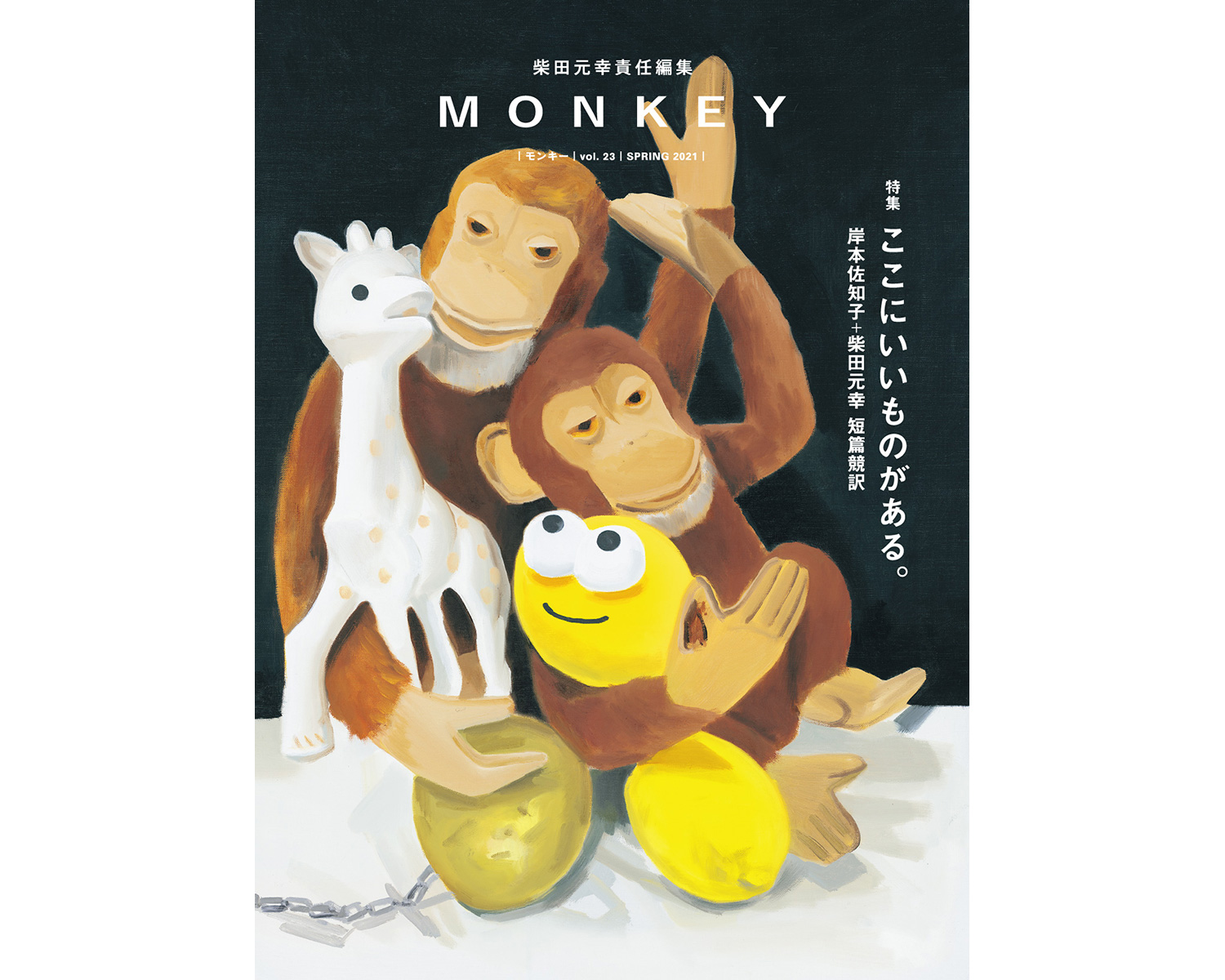
特集 ここにいいものがある。
1,200円+税
























Zorrie Underwood had been known throughout the county as a hard worker for more than fifty years, so it troubled her when finally the hoe started slipping from her hands, the paring knife from her fingers, the breath in shallow bursts from her lungs, and, smack dab in the middle of the day, she had to lie down. At first she carried out this previously unthinkable obligation on the worn leather of the daybed in the front room, with her jaw set, hands pressed tight against her sides, staring up at the end of a long crack that ran the length of the ceiling, or at the flecks of blue light thrown onto the legs of the dining room table by the stained-glass jay that hung in the south window. When after several minutes of this she felt her breath slowing and the blood flowing back out through her veins, she would ease herself up, shake her head, and resume whatever activity had been interrupted.
ゾリー・アンダーウッドは郡一帯で50年以上にわたり働き者として知られていたから、鍬の柄がとうとう手から滑り落ちるようになり、皮むきナイフが指からすり抜け、息が肺から浅く切れぎれに出るようになって、それから、真っ昼間に横にならずにいられなくなったとき、ゾリーは気に病んだ。昼間横になるなんて、これまでは考えられなかった義務だ。はじめ彼女はその義務を、表の部屋にある寝椅子のくたびれた革の上で遂行し、あごを引いて、両手をぎゅっと脇腹に押しつけ、天井を横切ってのびている長いひびの一端か、南側の窓に吊したステンドグラスのカケスがダイニングルームのテーブルの脚に投げかける青い光の斑点を眺めていた。これを何分かやって、息がゆっくりになってきて血が戻ってきて血管を流れ出すのがわかると、体の力を抜いて、頭を横に振り、さっき中断した仕事を再開するのだった。