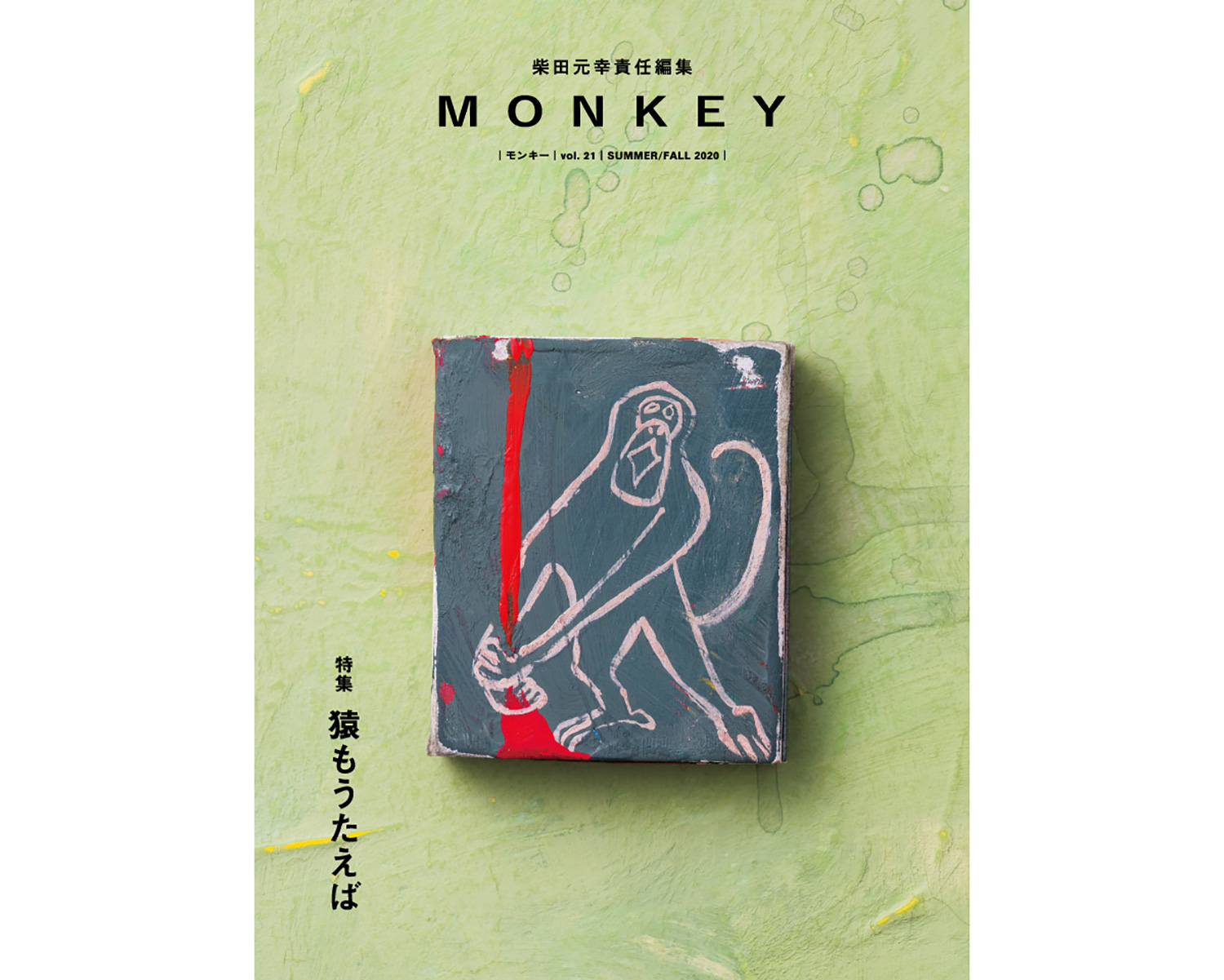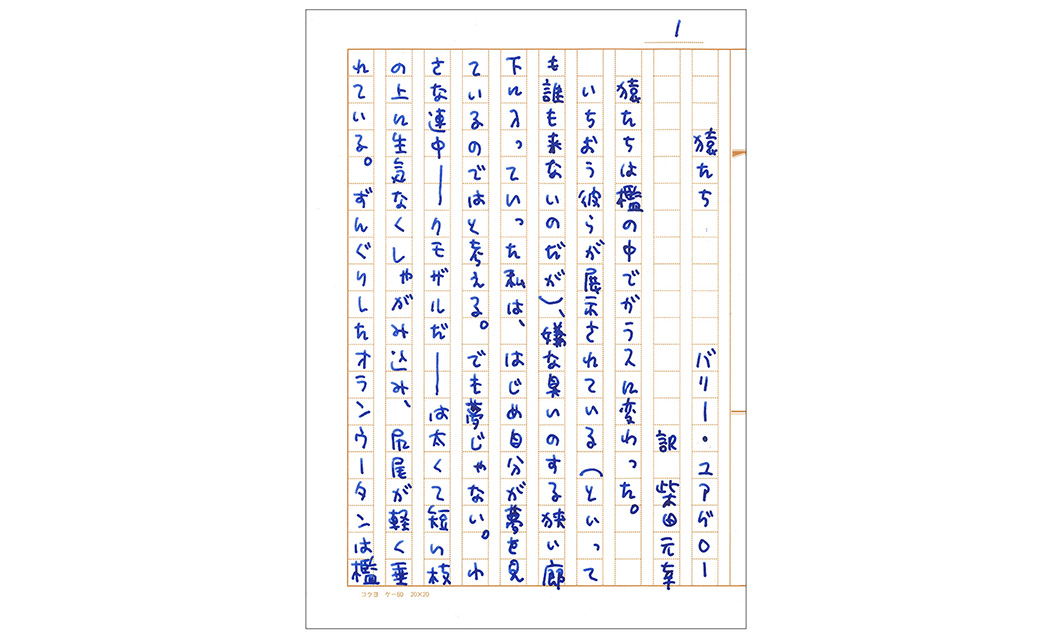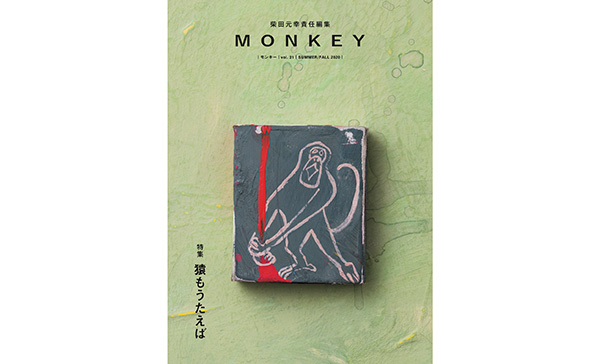文芸誌「MONKEY」2020年6月15日発売号は「猿もうたえば」と題し「うた」を特集。声や音が聞こえるアメリカの近現代詩から、ロックやブルースの歌詞、ネイティブ・アメリカンの口承詩、日本の説話文学までを射程に、“うた”としての詩や言葉にフォーカスしました。
今回刊行を記念して、特集に登場するさまざまな“うた”を柴田元幸がセレクトし、Spotifyプレイリストを作成。各曲への解説コメント付きでお届けします。Geeshie Wiley、The Smiths、Bob Dylan、Allen Ginsberg……。ぜひ本誌とともにお楽しみください。
柴田元幸による解説コメント
Geeshie Wiley, “Last Kind Words Blues”
グリール・マーカス「消える、忘れる」で徹底的に論じられている1930年のブルース。この世とあの世の境が取り払われたような、何とも不思議な空気。
Morrisey, “Everyday Is Like Sunday”
ブレイディみかこの小説「Everyday is like Sunday, isn’t it?」の背景に流れている曲。曲調も歌い方もマイルドだが、実はハルマゲドン来い! 原爆落ちろ!と世界を呪詛している。
Sonny Boy Williamson, “Bye Bye Bird” (Solo version)
*Spotify未配信のため映像にてお楽しみください
スチュアート・ダイベックの詩「ヴィヴァルディ」の最後で、ヴィヴァルディはハーモニカを口で覆っている。そのブルースハープは、こんな響きじゃないだろうか。
Joni Mitchell, “Coyote”
伊藤比呂美はコヨーテの声が聴きたくてアメリカに渡った。伊藤比呂美に多大な影響を与えたジョニ・ミッチェルのコヨーテはヒッチハイカーを拾う――「フリーウェイの白線の囚われ人を」。
The Smiths, “There Is a Light That Never Goes Out”
『全ロック史』の著者西崎憲が歌詞の面白さを推すのがザ・スミス。高揚も陶酔も独特の浮遊感に包まれて。でもしっかり泣かせもして。
Smart Went Crazy, “A Brief Conversation Ending in Divorce”
西崎憲がボーカルの面白さで推すのがスマート・ウェント・クレイジー。「離婚に至った短い会話」というこの曲のタイトルからも何となく想像できる、ナンセンスマンガみたいな面白さ。
Bob Dylan, “Like a Rolling Stone” (Live version, May 1966)
チャールズ・ブコウスキーの「ボブ・ディラン」は、近所のカップルがボブ・ディランをガンガンかけてるからディランがタダで聴ける、という詩。そこで鳴ってるディランはこんな感じか—— エレキに転向した彼を野次る観客に負けまいとPlay it fuckin’ loud!(デカい音で行くぞ!)とバンドをけしかけて歌い出す。
Elvis Presley, “Hound Dog”
グリール・マーカスが「消える、忘れる」で言及しているエピソード—— 1957年、エルヴィス・プレスリーはシアトルでのコンサートで国家を歌うと宣言して観客を起立させ、「ハウンド・ドッグ」を絶叫しはじめた。これは史実である。
Jimi Hendrix
“Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band”
“All Along the Watchtower”
そのプレスリーのライブを聴いた14歳のジェームズ・マーシャル・ヘンドリックス少年は、10年後に史上最大のギタリスト、ジミ・ヘンドリックスとなる。これは史実である。「サージェント・ペパーズ」と「見張り塔からずっと」……ビートルズとディランのカバーを同じアルバムでやってしまって許されるアーティストはジミヘンしかいない。
Allen Ginsberg, “A Supermarket in California”
これは詩の朗読。たくましさよりも頼りなさ、おおらかさよりも傷つきやすさが前に出ているが、しなう茎の強さみたいなものも感じさせる。
【新訳】『吠える その他の詩』(訳・柴田元幸)