
毎月、猿が仲間に「ここにバナナがあるぞー」と知らせるみたいな感じに、英語で書かれた本について書きます。新刊には限定せず、とにかくまだ翻訳のない、面白い本を紹介できればと。
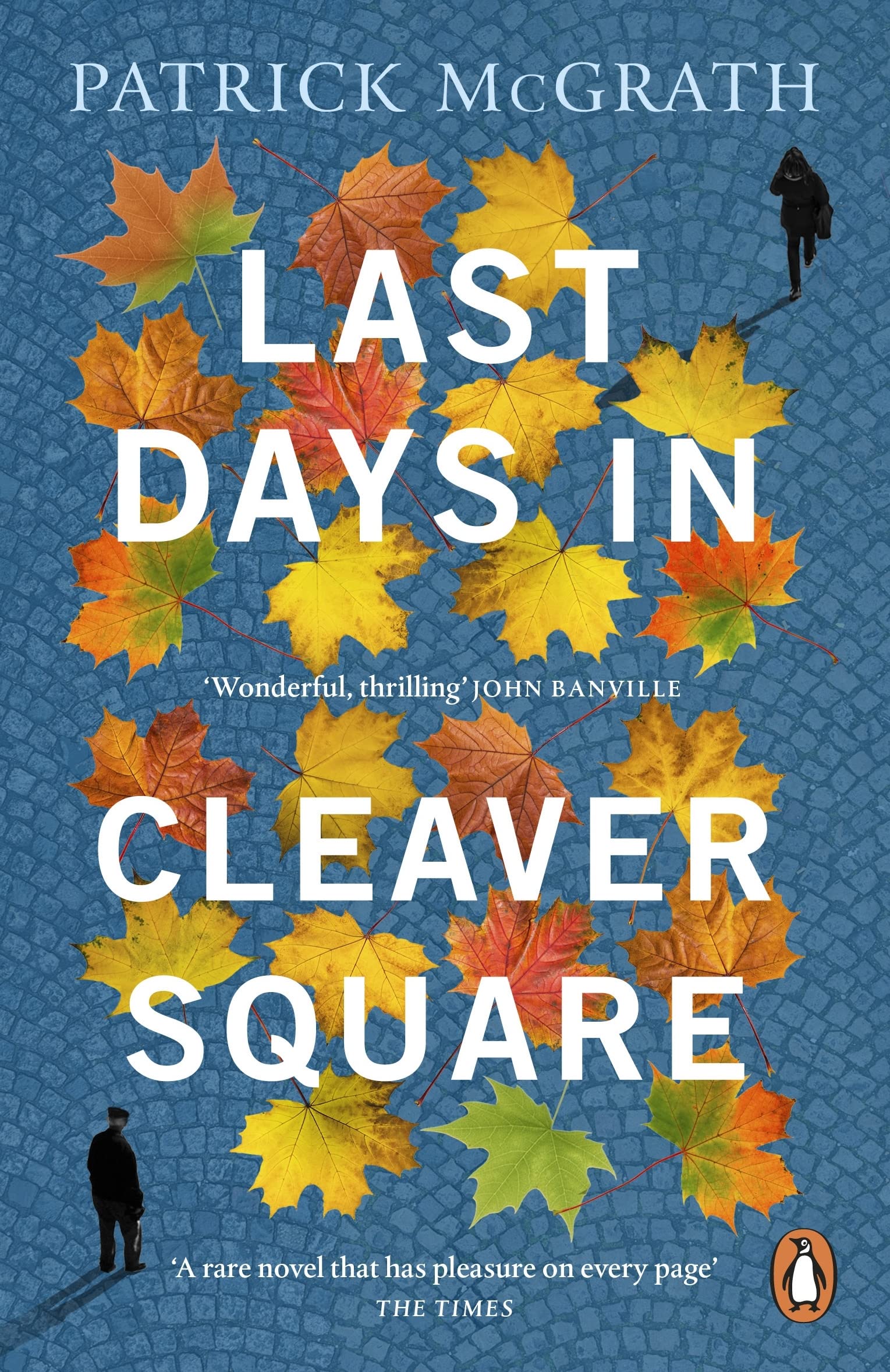
作家パトリック・マグラアの父親は精神病院の院長だった。患者たちは幼いパトリックの遊び相手だった。
These were the friends of my early boyhood, men who twenty years earlier would still have been called ‘criminal lunatics’. The first I met was Frank, who built me a swing that hung from an iron bar that he made in the hospital workshop and set high between a pair of tall pines. I treated Frank as an uncle, following him around while he went about his work, chattering away. In the autumn, when he filled his wheelbarrow with dead leaves he would let me ride on top of the heap, clutching a garden fork and shrieking like a little sea god in his chariot. I once asked Frank what he had ‘done’, and he shook his head and told me, kindly, sadly, that it was ‘very bad’ – but said no more.(Patrick McGrath, “A Childhood in Broadmoor Hospital,” Granta, vol. 29, 2008)
こうした、当時よりほんの二十年前でもまだ「犯罪性精神異常者」の烙印を押されたであろう人たちが、幼かった私の遊び友だちだった。最初に仲よくなったフランクは、私にブランコを作ってくれて、それを病院のワークショップで作った鉄棒につないで、高い二本の松の木から吊してくれた。私はフランクを叔父さんと思って接し、仕事にいそしむ彼に、ペチャクチャ喋りながらくっついて回った。秋になって、手押し車が落葉でいっぱいになると、フランクは私を葉っぱの山の上に乗せてくれた。私は熊手を握りしめて、戦車に乗った小さな海神にでもなった気分で、きゃあきゃあ声を張り上げたものだ。あるとき、何を「やった」せいでここに来たのかと訊ねると、フランクは首を横に振って、優しい、悲しげな声で、「すごく悪いこと」をしたんだよと言ったが、それ以上は何も言わなかった。(パトリック・マグラア「ブロードムアの少年時代」、柴田編訳『燃える天使』角川文庫 所収)
こうした経験が作家パトリック・マグラアを作ったと言っても過言ではないだろう。マグラアの小説の主人公はたいてい精神に何らかの問題を抱えていて、他人には明かせない秘密を持っている。むろんその「他人」の中には読者も含まれる。だから彼らの語りの中には多かれ少なかれ虚偽がある。読者は語り手の言葉の中の事実と虚構とを峻別し、隠された真実を探りながら読む。これがマグラア作品を読むひとつの醍醐味である。といっても作者は、虚偽を冷酷に暴くことを目的にはしていない。むしろ、虚偽が明らかになった上で、虚偽にすがらざるをえない人物に共感するよう我々は促されている。代表的なマグラア作品で、クローネンバーグによって映画化もされている『スパイダー』について、若島正はこう書く。
わたしは最初に、「信頼できない語り手」という技巧について述べた。しかし、この用語は、読者が語り手に対して信頼を置いてはならないということを意味しない。信頼できないのはあくまでも「語られていること」であり、登場人物の一人として、人間としての語り手には、なにがしかの信頼を置かなければ、わたしたちがそのような屈折した小説を読む意味はほとんどないだろう。語り手の精神的崩壊を、妄想を、狂気を、抑圧を、なにがしかの共感を持って読むことがなければ、すべてはたわごとに等しいだろう。マグラアの小説が愛読者を獲得しているのは、そこに描かれている出来事が異常だからではけっしてない。ある種の狂気に取り憑かれた人間、歪んだ人間を描いて、そこに共感をおぼえさせる不思議な力があるからだ。そしてこの『スパイダー』も例外ではない。
その共感がもともとブロードムアで培われたと想像して、おそらく誤りではないだろう。
が、2021年刊、目下のマグラア最新作『クリーガー・スクウェアでの最後の日々』は、この基本図式から微妙にずれてきていて、非常に興味深い。
主人公の老詩人フランシス・マクナリーは、若者だった1930年代に、当時多くの理想主義的な若者がそうだったように、スペイン内戦に赴いて反ファシズムの側に立って行動した。そして1975年のいま、ロンドンのクリーガー・スクウェアなる一画に住む彼は、家の内外で時おりフランコ将軍の——いまやすっかり老いて死の一歩手前まで来ているファシストの——生霊を見る。が、使用人の女性もどうやらその生霊を見ているようだし、明らかに「正常」の側に立つ代表たるフランシスの娘ジリアンも生霊が放つ異臭を実際に感じている。つまりこの話は、合理的には説明できないゴースト・ストーリーの要素を含んでいる。そう思って読むと、いまや世間的にはほとんど忘れられた詩人であるフランシスの過去に興味を持ち、スペインでの体験を聞こうと毎日のようにやって来る若い新聞記者も、生身の人間というよりはどこか幽霊のように感じられる。
「老い」も今回は重要な要素である。老いた詩人にもいまや死の影は忍び寄り(彼の名がフランコ将軍の姓と似ているのは偶然ではないだろう——彼らはある種の分身関係にある)、記憶の濃淡もまだらである。ありていにいえば、いささか呆けてきているので語りがいまひとつ信頼できない。そのあたりが、69歳の読者(柴田)には非常にリアルである。作者マグラアも1950年生まれだから、この小説を書いていたときはおそらく60代後半、むろん自伝的ということではないが、今回はいつもほど作者と語り手のあいだに距離を感じさせない。ひとまず「正常」の側にいる作者が何らかの「異常」を抱えた人物を救済する視線で見下ろす、という感覚は薄い。作者が自分の老いを素材に使っている、とは言わないが、「明日はわが身」くらいの感触は十分にある。Last Days in Cleaver Squareというタイトルが、少年時代を綴った”A Childhood in Broadmoor Hospital”と同じ構造(“時期 in 場所”)になっているのはべつに意図的ではないだろうが、一周ぐるっと回ってきた感は確かにある。
とはいえ、もちろんというべきか、今回の主人公も暗い秘密を抱えていて、それが小説を動かす核になっている点はいままでのマグラア作品と変わらない。フランシスの場合それは、スペインでの体験、とりわけ彼が愛したアメリカ人男性ドク・ロスコーとその死に関わるものであることがだんだん見えてくる。
Eventually I was shipped out and by way of Barcelona I got back to England. For years the thought was never far from me, that it should have Doc who went home. I never attempted to find his grave. I never returned to Spain to make enquiries as to the whereabouts of those who had been shot in the monastery of Saint Eulalia. And even if I had, how would I tell his bones from another’s? I could not have done so. But did that even matter? Would not one skull be as good as another? One man’s ribcage, caked with soil, to serve as well as his, and being exhumed, and cleaned, and coffined, and a patch of holy ground found in which to be reinterred – given at least the small uncertain solace of a decent burial under the weeping gaze of a loyal friend? Or rather: a disloyal friend. Thus do I torment myself. Thus do I measure myself, that I did not save him. He would have done it for me. He did. (Last Days in Cleaver Square, Ch. 30)
やがて私は船に乗せられ、バルセロナ経由でイングランドに帰った。何年ものあいだ、思いは決して私から離れなかった——帰国すべきはドクだったのだ、という思い。私は彼の墓を見つけようとはしなかった。スペインにも戻らず、聖エウラリア修道院で銃殺された者たちの行方を問い合わせもしなかった。かりにそうしたとしても、どうやって彼の骨を他人の骨と見分けられよう? できるわけがない。でもそれも問題だろうか? どの頭蓋骨でも同じことではないか? 泥がこびりついた誰の胸郭だろうと、彼のと変わらず十分役に立つ。発掘され、綺麗にされ、棺に入れられ、ふたたび埋葬すべき聖なる地面も見つかり、忠実な友の、涙まじりのまなざしの下、まっとうな埋葬を受ければ、曖昧ではあれささやかな慰めではないか? いや、忠実な友じゃない——不実な友だ。かように私は自分を苛む。かように私は、彼を救わなかったことで自分を測る。彼なら私のためにやってくれただろう。というか、事実そうしてくれたのだ。
友を救えなかった——裏切った——自責の念。そうした事態を引き起こした根源であるフランコへの激しい怒り。「正常」の視点から父の奇行を責めるものの本物の愛情も感じさせる娘ジリアンとの確執。幽霊のような若手新聞記者とのやり取り。一日で唯一の楽しみであるシェリーを飲みに行くパブの中の澱んだ空気。背後霊のようにいつもひっそり陰にいる無口な使用人ドローレス・ロペス(フランシスはスペインで、小さな女の子だった彼女を瓦礫の中から救ったのだ——母親は救えなかったけれど)の不思議な存在感。“a cantankerous animal”(つむじ曲がりの動物)と紹介される、いつも不機嫌そうな様子が実に味わい深い老猫ヘンリー・スレッショルド。そうした要素がすべてあわさって、物語はフランシスが、フランクがついに死につつあるスペインへ向かうことでクライマックスを迎える。
そしてフランシスはスペインで、実に馬鹿馬鹿しくも痛快なことをやってのけ、ふだんはニコリともしないドローレス・ロペスも狂ったように笑い出す……このあたり、いままでのマグラア作品にはない爽快な解放感が広がるのだが、これについてはさすがに「ネタバレ」になるので想像していただくしかない。
最新情報
〈刊行〉
MONKEY30号「渾身の訳業」発売中。
MONKEY31号「読書」(仮題)10月15日発売予定。
MONKEY英語版第4号「MUSIC」10月6日発売予定。
アレクサンダル・ヘモン『ブルーノの問題』秋草俊一郎と共訳 書肆侃侃房 秋刊行予定。
〈イベント〉
9月19日(火)~20日(水)レアード・ハント『インディアナ、インディアナ』刊行記念朗読ツアー in 四国 19日7:30-9pm「本の轍」/20日7:30-9pm「本屋ルヌガンガ」
詳細はこちら。
9月29日(金)7-8:30pm 『セミコロン かくも控えめであまりにもやっかいな句読点』(左右社) 発売記念トークイベント 「翻訳家も悩ますセミコロン?」萩澤大輝・倉林秀男と @青山ブックセンター
詳細はこちら。
9月30日(土)11am-12pm 「いま、これ訳してます」part 41
オンライン朗読会 手紙社主催
詳細はこちら。
9月30日(土)6:30-9pm「月にまつわる翻訳夜話」
小島ケイタニーラブと @浅草 梅と星
詳細はこちら。
〈配信〉
コロナ時代の銀河 朗読劇「銀河鉄道の夜」 河合宏樹・古川日出男・管啓次郎・小島ケイタニーラブ・北村恵・柴田
《新日本フィル》朗読と音楽 ダイベック「ヴィヴァルディ」 朗読:柴田 演奏:深谷まり&ビルマン聡平
ハラペーニョ「二本のマッチ」朗読音楽映像 ロバート・ルイス・スティーヴンソン「二本のマッチ」/ハラペーニョ=朝岡英輔・伊藤豊・きたしまたくや・小島ケイタニーラブ・柴田
























