日仏友好160周年を迎え、秋ごろからNHK にて国内でも人気の作品『ラディアン』(ユーロマンガ刊)がアニメ化するなど、ますますの盛り上がりを見せるBD。今回お話を伺うのは、クールな黒猫私立探偵が主人公のハードボイルドマンガ『ブラックサッド』などの翻訳を手がける大西愛子さん。もともとマンガには詳しくなかったという大西さんがBD翻訳に携わることになったきっかけや、スイッチ・パブリッシングから刊行中の村上春樹さんの短篇をBD化した「HARUKI MURAKAMI 9 STORIES」について語っていただきます。

大西愛子(おおにしあいこ)
1953年生まれ。翻訳家。主な訳書にステファヌ・マルシャン著『高級ブランド戦争 ヴィトンとグッチの華麗なる戦い』、ジョルジュ・ルルー著『グレン・グールド 孤独なピアニストの心象風景』をはじめ、ニコラ・ド・クレシー『氷河期』、マルク=アントワーヌ・マチュー『レヴォリュ美術館の地下』、ギベール&ルフェーヴル『フォトグラフ』、エンキ・ビラル『ルーヴルの亡霊たち』などBDの訳書も多数。カナレス&ガルニドの代表作である『ブラックサッド』シリーズについては2005年の初版から翻訳を担当。
第2回 フランス人から見た村上作品
「HM9S」の中には日本人である我々には違和感のある描写も登場しますが、それはなぜなのでしょうか。大西さんの分析を聞いてみます。
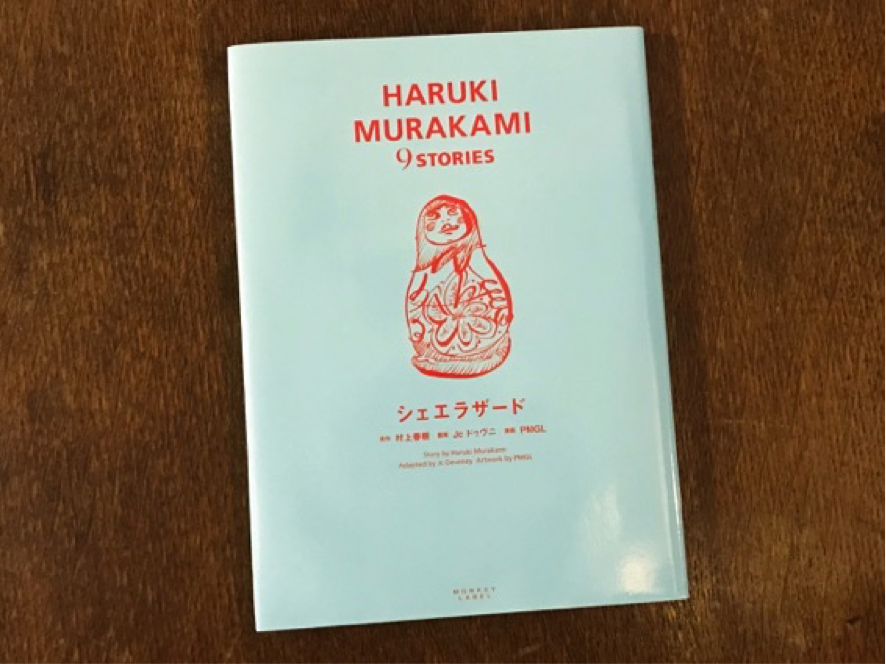
“約束事”から離れて日本をみる面白さ
——ここからは「HARUKI MURAKAMI 9 STORIES」についてお聞きします。作者の2人は、村上作品には漫画にするのに最適なエッジの効いた登場人物や、ファンタジー的なストーリーなどヴィジュアル化に最適な要素が揃っていると考えているのですが、大西さんはどのようにお感じですか。
大西 私はむしろ逆なんですよ。
——えっ。逆とは!
大西 私の中で文学作品とは、行間を読者が想像や妄想で埋めるという醍醐味が多かれ少なかれあると思います。村上さんの作品は特にその作業が必要というか、自然とさせられるものが多いと感じるんですよね。
——なるほど。
大西 私自身、そのように登場人物の顔であったり、状況を想像することが好きなんです。基本的に文学作品がドラマ化や映画化、コミック化されることによって、イメージはある程度固定化されますよね。しかもそれは、その作品が生まれた環境、制作者というバイアスを通したものに置き換わることが多い。この「HM9S」で言えば、フランス人の作者2人というフィルターを通した日本が描かれるわけです。フランス人アーティストから見た村上作品の世界に違和感を抱く人もいれば、逆にそこがこの作品の魅力とも言えます。
——違和感こそ魅力。
大西 それはフランスで日本のものを見たときにも言えることです。フランスでは日本のアニメがとても人気で、私がパリで子育てをしていたときにずっと『キャンディ・キャンディ』が放映されていました。キャンディは金髪の女の子のキャラクターなので、フランス語を話すことに関しては、少しも違和感はありません。けれども、ある話でキャンディが偉い人の部屋から退室するときに「ぺこり」とお辞儀をしたんです。それを見たときに大きな違和感がありました。
——フランス人は退室するときにお辞儀をしないんですね。
大西 そう。それは日本の感覚で日本人の動作なんです。でも、日本でその様子を見ると、私もアニメも日本という“約束事”の中にいるから違和感がない。けれどもフランス語を話すキャンディがお辞儀をすると、ものすごく違和感があって。これは日本語でしゃべっていたときには気がつかなかったことだと思ったんです。
——約束事から一歩踏み出して、外の視点から見ることで、これまで気がつかなかった作品の違和感に気がつくわけですね。
大西 ただ、この「HM9S」は試みとしては非常に面白い。外国人が読む村上春樹というものが素直に出ているなあと感じます。彼らが感じる村上作品へのイメージと私たち日本人が感じるイメージとでは、どこか違う点がある。その違いがこういった形でストレートに出てくると面白いじゃないですか。異文化交流の醍醐味というか。日本語の本が外国語に翻訳されたものを、さらに日本語に翻訳するなんてことは小説のみだったら絶対にありえないことですから。
行間から感じる村上作品の洗練された雰囲気

——「HM9S」ではどのような点に、日本人とフランス人のイメージの違いを感じますか。
大西 例えば登場キャラクターが原作で描かれているよりも老けて見えていたり、“文字通り”疲れた雰囲気を漂わせていたり。
——“文字通り”とはどういうことでしょう。
大西 例えば「HM9S」の『かえるくん、東京を救う』では、主人公の片桐は確かに40代でしょぼくれていて、ハゲかかっているおじさんのように描かれていますが、原作を読んでイメージする男性像って、こんな風にしょぼくれた男性じゃないんです。これは村上さんの作品全般に通じる私のイメージですが、村上さんの作品でどんなに悲惨なことが書いてあっても、どこか都会的で、どこか洗練されていて、どこかおしゃれなんですよね。
——分かります。その差はいったいどこから生まれるのでしょう。
大西 それはおそらくフランス語訳の持つ雰囲気からきているのかなと思います。私たち日本人は先ほど挙げたイメージを行間から感じ取りますが、もしかしたらフランス語に訳されるときに、そういった“文体の持つ雰囲気”がすっぽりと抜け落ちてしまっているのかもしれません。
翻訳者は裏切り者?
大西 「翻訳者は裏切り者」とよく言われるのをご存知ですか?
——初めて聞きました。どのような意味なのでしょう。
大西 格言というほどじゃないのですが、元々はイタリア語で「Traduttore, traditore(トラドゥットーレ、トラディトーレ)」。要するに「翻訳者はどのように忠実に翻訳したとしても、どこかしらで元々の作品を裏切ってしまっている、全てを翻訳し切ることはできない」、ということを表している言葉なんです。2つの国において、100パーセント一致する言語というものはこの世には存在しない。一つの単語が内包する意味を片方の国では一つの言葉で表現できても、もう一つの国の言葉ではどうしても表現しきれない部分がある。だから、結局のところ翻訳というのは、翻訳者の解釈を通してでしか見ることが出来ない。読者はそういったものを、作品を読みながら受け取っているということになるわけですね。
——大西さんが翻訳されるときは、ご自分の解釈をなるべく普遍的なレベルまで削り込んで訳されているのでしょうか。それともご自分で読まれたときのイメージを素直に受け入れて、日本語に落とし込んでいくのでしょうか。
大西 私は原作者へのリスペクトが強いので、原作者が何を言いたかったのかを徹底的に調べて訳そうと試みています。翻訳者は原作をリスペクトしなければいけない。ただ、“奴隷”にはなってはいけないとも思うんですね。どちらかといえば、原作を俯瞰するような目で見て、原作のもつ全体的なイメージを含めて訳さなければいけない。私はどうしても細かいことにも目が行ってしまって、引きずられてしまう傾向があるので、作品全体のイメージを包括することがまだ欠けてしまっているかなとは思います。
——翻訳者の方々はそういったジレンマを抱えているのでしょうか。
大西 みなさんジレンマは抱えていると思いますけどね。結局創作と違って、どうしても原作に縛られる。場合によっては原作者がうっかり書いてしまったことにまでもこだわってしまったりもしますから。
——「奴隷になってはいけない」という表現、格好良いです!
大西 なってはいけないと思いつつも、なってしまっているんですけどね(笑)。でも、絶対にリスペクトは必要。それが無ければ翻訳しないほうがいいかな。原作にリスペクト出来ないのだったら、作品を翻訳してはいけない気がする。
——愛情が大切になってくると思います。
大西 そうですね。だから自分が持ち込んだ作品というのは思い入れがあるから、割とすんなりとリスペクトした訳が出るんだと思います。けれども、時には他の人から注文されて翻訳する作品などもあるので、そのときにどうするかが重要ですね。
——そのときは好きになろうという努力から始まるのでしょうか。
大西 好きになろうというよりも、出来るだけ読み込む。どうしてこの人はこう表現しているのだろうと。それはBDでも普通の書籍でも同じだと思います。
(つづく)























