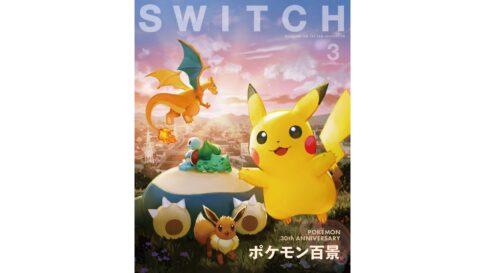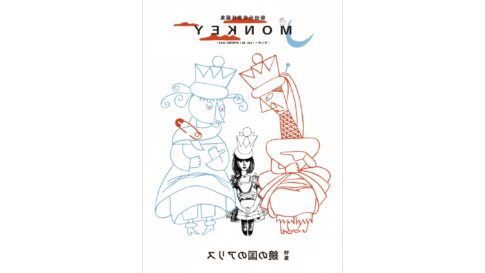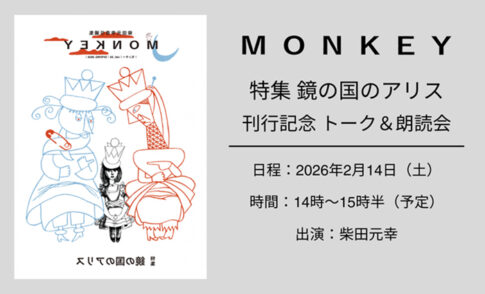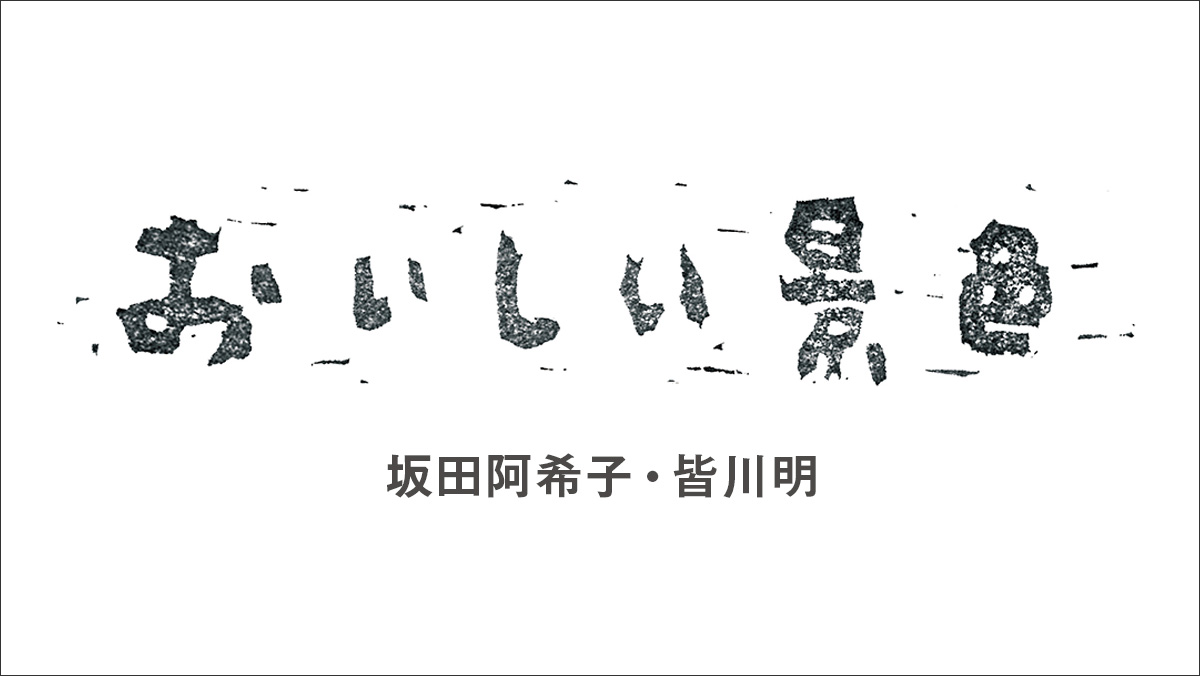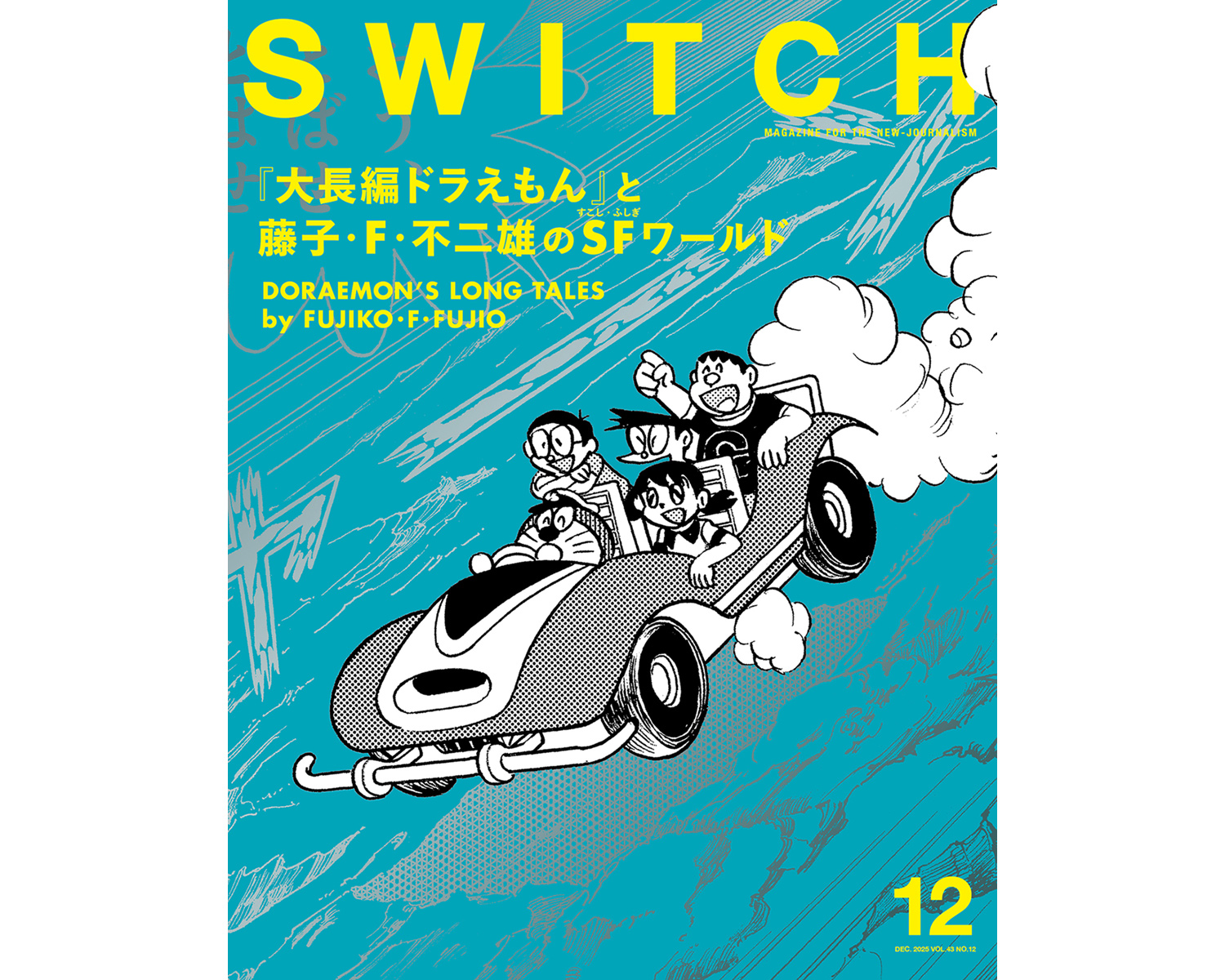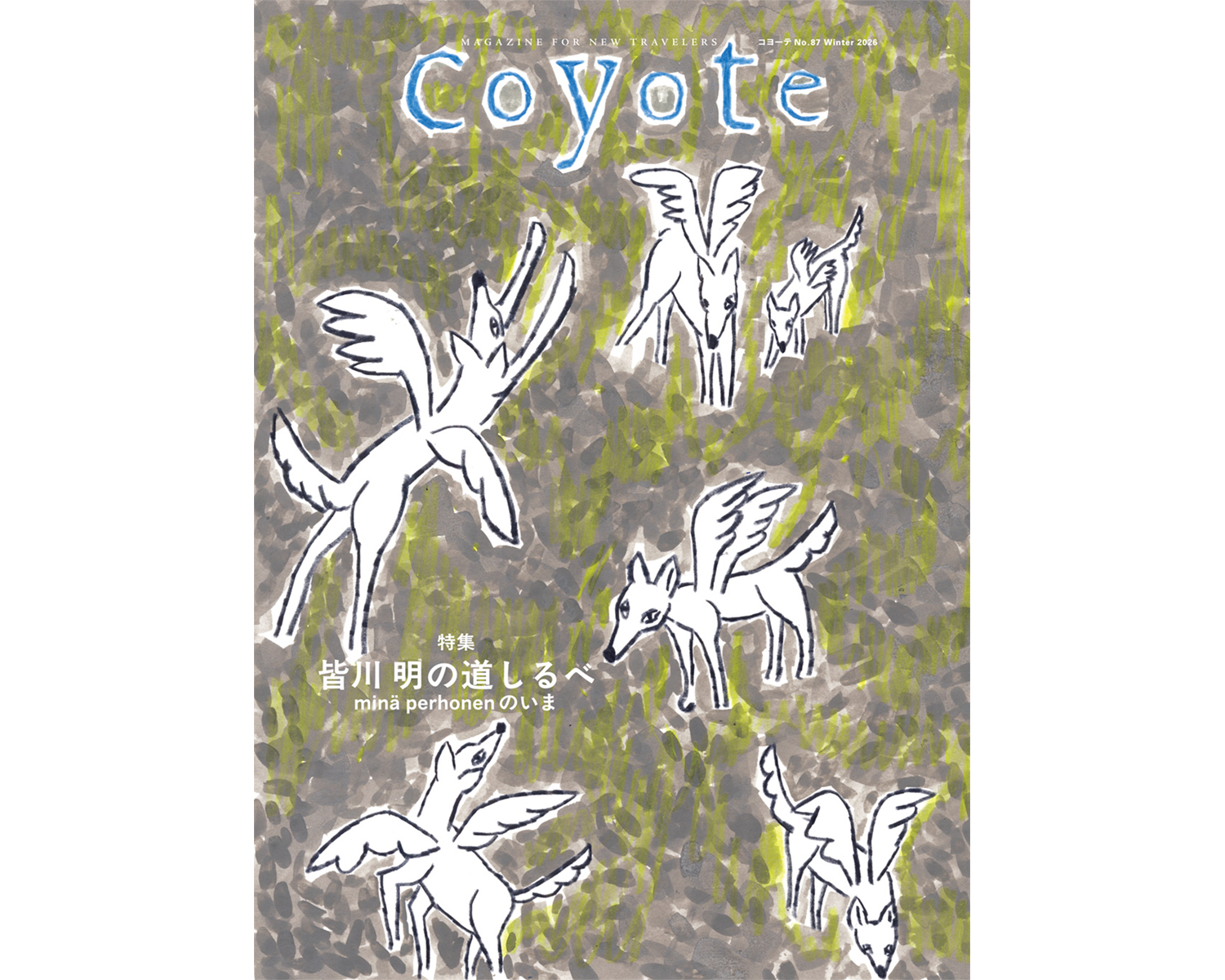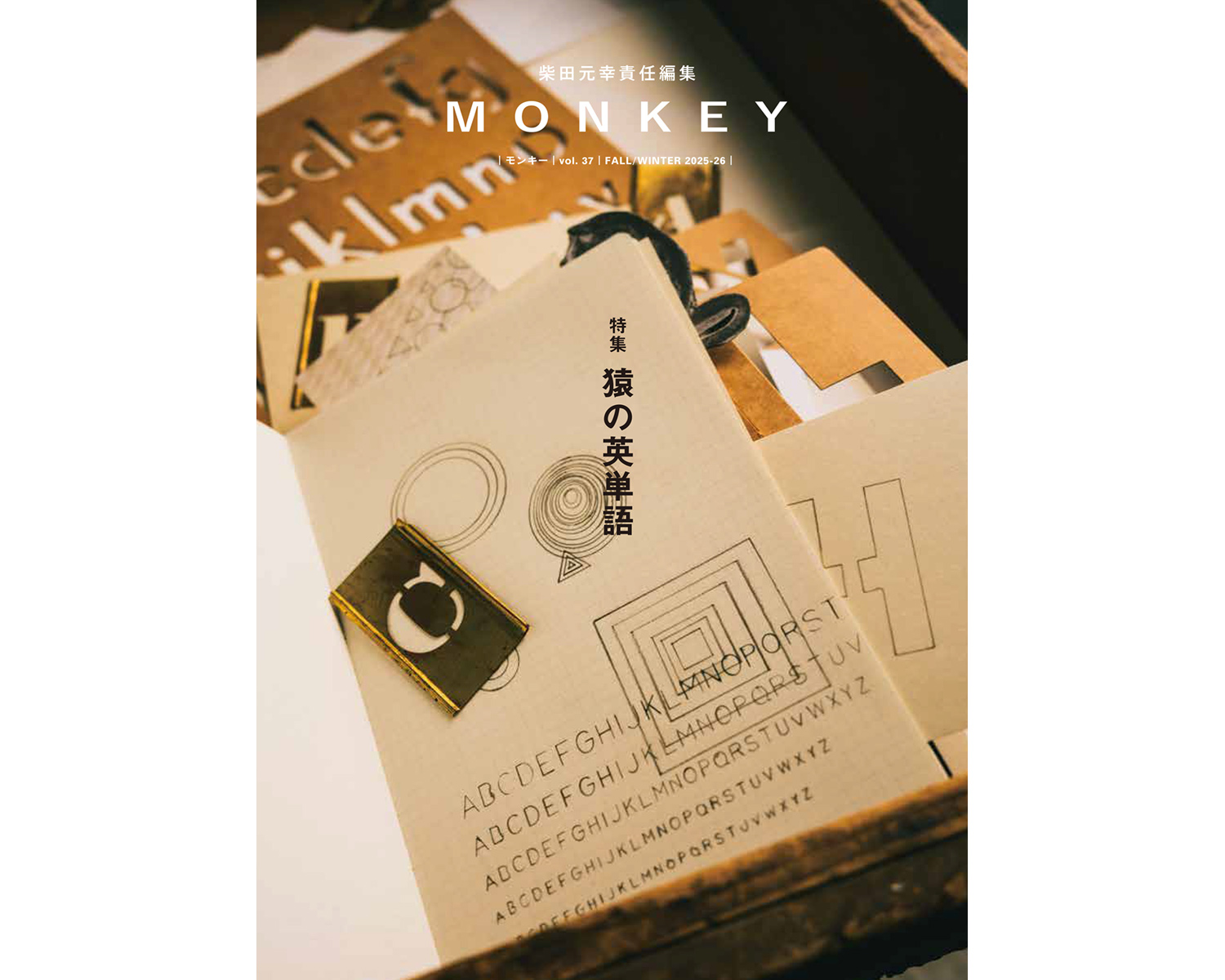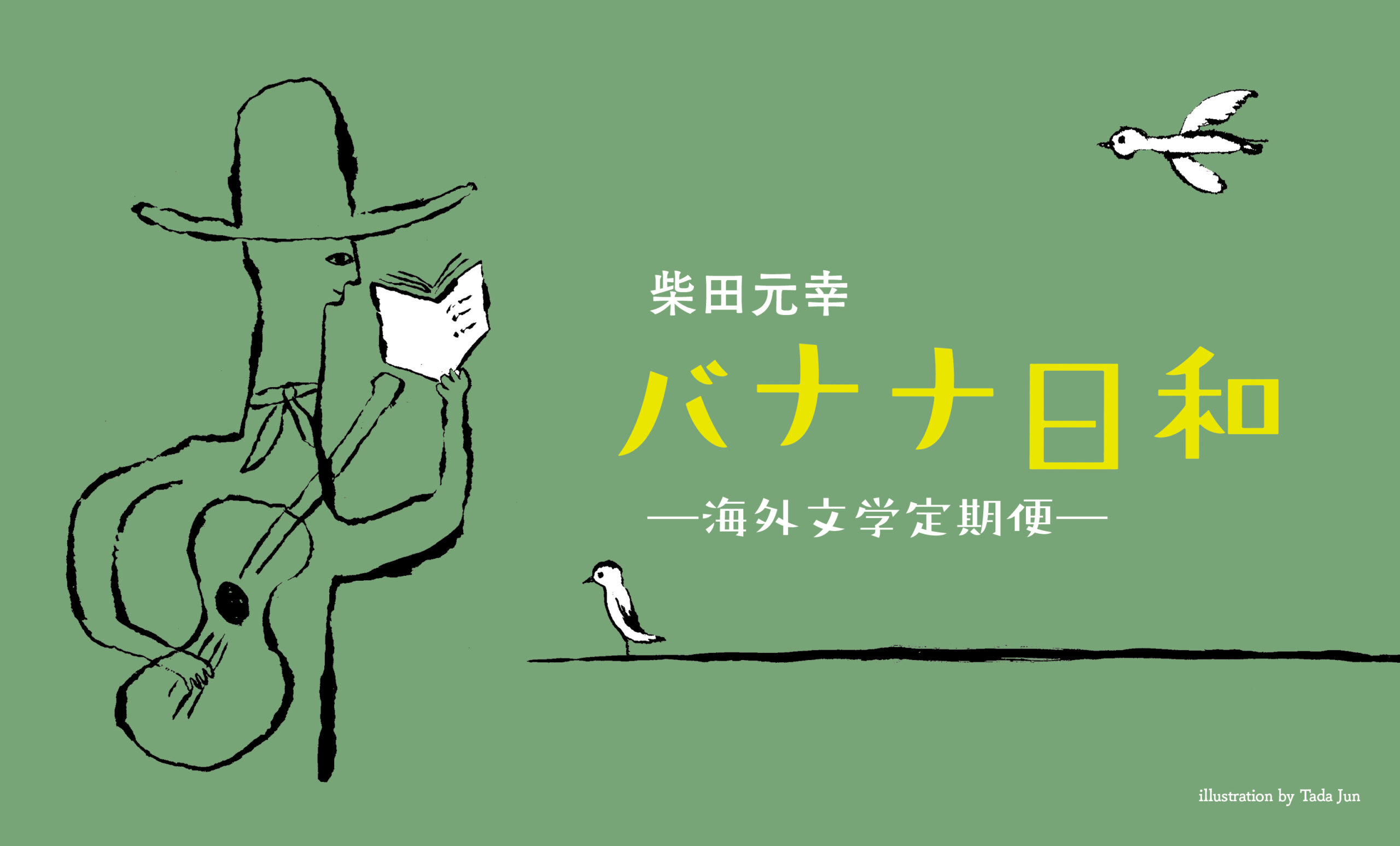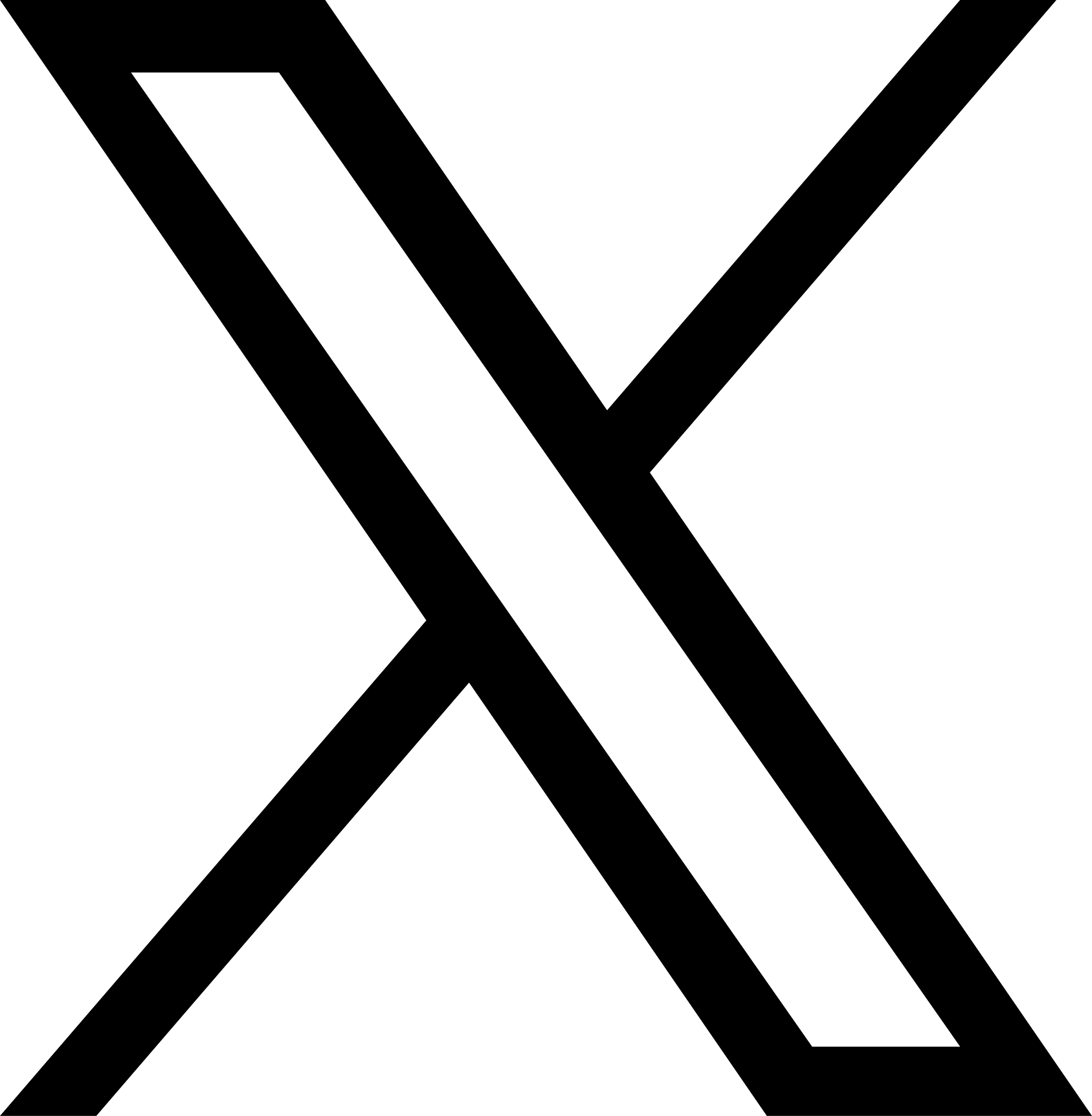2005年に誕生したボルドーワイン「クラレンドル」。ワイン王国フランスの最高峰とも言われるシャトー・オー・ブリオンの系譜に連なる、特別なワインだ。ワイン好きを自認する世界的ジャズピアニスト上原ひろみが、「クラレンドル・ルージュ」が注がれたグラスを片手に、音楽、ピアノ、そしてワインについて語る ——
![上原ひろみ[ワインの向こうに、人や街が見える]](https://www.switch-pub.co.jp/wp-content/uploads/2025/11/sw4312_clarendelle_01.jpg)
INTERVIEW 上原ひろみ
ワインの向こうに、人や街が見える
自分の音楽を届けに、小さなホール、遠くの街にも旅する上原ひろみ。地元のワインや旬の食べ物が、上原とその土地を繋ぐ
HAIR & MAKE UP: KAMIKAWA SEIJI
TEXT: IMAI EIICHI
ピアノのそばのサイドテーブルに、「クラレンドル・ルージュ2018」のボトルと、その赤ワインが注がれたワイングラスを置き、上原ひろみのポートレイトを撮る。「赤ワイン、大好きです」と上原は微笑みを浮かべながら言い、慣れた手つきでグラスを持ち上げると、顔に近づけ香りを確かめる。
「旅が多いので、各地でその土地のワインをいただくことが多いです。ヨーロッパ、特にフランス、イタリアの人たちは、自分が暮らす土地の食やワインについて、強い自信と誇りを持っていますよね。コンサートで行くと、迎えてくれた地元の方たちは、私が赤ワインを好きだということを知ると、張り切って自慢の1本を用意してくれたり。演奏のために行きますが、その土地の食とワインをいただきながら、地元の人たちと語り合う時間は、喜びです」
そして上原は、何年か前にボルドーを訪れた時のエピソードを話してくれた。
「コンサートが終わって、関係者全員での遅い夕食のために打ち上げのレストランへ行ったら、ずらっとボルドーワインのボトルが並んでいて。イベントのオーガナイザーの方が、上原さん、さぁどれからいきますか、みたいな。びっくりしつつ、それはとても楽しい夜でした」
上原が拠点にするアメリカもワインの一大生産地だが、「フランスは、ワインがもっと近くにある感じがする」と彼女は言う。
「フランスでツアーをしていると、泊まったホテルの裏がブドウ畑、ワイナリーという時もあって、ワインづくりの現場が日常に近い感じがします。一本のワインボトルの先に人の姿が見えるというか。ブドウ畑で働いている人、ワインをつくっている人、その村や街の人々の姿もうかがえる。フランスでは、ワインによって、その街や土地がぐっと近くなりますね」
人と人との境界を取り払い、近づけてくれるワイン。ボーダーを越えて、その土地の暮らしと文化を教えてくれる。

クラレンドルは、音楽や芸術に寄り添っているワインでもある。たとえば、アカデミー賞授賞式のセレモニーでは、2023年から3年連続、クラレンドルのワインがふるまわれた。クラレンドルはまた、上原もプレイした「モントルー・ジャズ・フェスティバル」の海外ワイン・スポンサーを務めていて、イベントの支援をしながら、「音楽とワインの融合」に取り組んでいる。
「ジャズとワインを絡めたイベントに出ることもある」と上原は言う。「ワインのつくり手の方に直接会う機会もあります。そういう人たちの話を聞くのが私は大好き。こだわり抜いてひとつのものをつくっている方の話には気づきや発見がたくさんあるし、これは音楽も同じですが、自分が大好きでそれをつくっている方が目をキラキラさせながら語っているのを見ると、そのワインが何倍も美味しく感じます」
この数日前まで上原はコンサートでアメリカ各地を旅していた。演奏の旅はその後、ヨーロッパへと続く。「私のピアノが聴きたいという人がいれば、どこへでも行きたい」と上原は目を輝かせて言う。
「そこが小さな町でも、無名のホールでも、私は気にしない。誰かとご縁が繋がる瞬間を大切にしています。今も飛行機は苦手ですが、どこか遠くの、自分が知らない場所へ行くのは好きです。自分が当たり前と思っていたことが、全然違うんだと気づかせてくれるから」
この11月の終わりからは、「Hiromi’s Sonicwonder JAPAN TOUR 2025 “OUT THERE”」で、日本全国を旅していく。ラーメン好きなSonicwonderのメンバーと各地のご当地ラーメンを食べ、打ち上げでワイングラスを傾けることもあるだろう。
「やはり誰かと一緒に飲むのが、百倍楽しいですね。仲間と『美味しいね』と言い合えるのは、最高に幸せだし、楽しい時間です。ツアー中は、その土地の美味しいものを食べることを大切にしています。四月にヨーロッパへ行けばアスパラガスばかり毎日食べますし。その場所の旬なものを、その地の料理でいただくのが、健康にも良い気がします。そこにワインが一緒にあれば、最高ですよね」
撮影が始まる直前、上原は、部屋にアップライトのピアノがあるのを見ると、すっと近づき、挨拶するように、片手でやさしく鍵盤を叩いた。インタビューの最後、彼女に、音楽雑誌の記事で読んだ、「ピアノは自分にとって美味しいご飯に似ている」という言葉の真意について問うと、「どういう流れでそう表現したか、わかりませんが」と言いながら、こう語った。
「確かにうまく弾ければ美味しいご飯かもしれない。ピアノはご褒美であり、チャレンジであり、けっして飽きさせられることのない永遠に面白い相手、というか。常に興味深い存在であることは間違いありません。いつも私をワクワクさせてくれ、私の好奇心を常にかき立ててくれる存在。ご飯はお腹いっぱいになると食べられないけれど、ピアノはずっと食べられるというか。やめられないし、嫌になることがない。ピアノにもっともっと近づきたいし、知りたい。なんだろう、ピアノと一体感のある時がもっと増えていくといいなっていうのは、いつも感じています」

[衣装]ワンピース/LIMI feu(ヨウジヤマモト プレスルーム 03-5463-1500)
INTERVIEW ナタリー・バソ・ドウォーキン
ワインは、人と人とを結ぶもの
クラレンドルのワインについて語るため、初めて日本へやって来た。ワインに魅了された彼女は、ワイン醸造学の国家資格を取得。ワインを愛するクラレンドルのつくり手
![ナタリー・バソ・ドウォーキン[ワインは、人と人とを結ぶもの]](https://www.switch-pub.co.jp/wp-content/uploads/2025/11/sw4312_clarendelle_04.jpg)
TEXT: IMAI EIICHI
「ボンジュール、サバ?」とカジュアルなフランス語で挨拶し、続けて英語で、疲れていませんか、時差ボケは大丈夫ですか、と訊ねると、ナタリー・バソ・ドウォーキンは、笑顔で「ノー・プロブレム! 飛行機の中でぐっすり寝たから、快適よ」と元気に答えた。インタビューと撮影は午後だったが、ナタリーはその日の朝、羽田空港に到着したばかり。しかもこれが、初めての日本だという。
フランスの歴史あるワイン・グループ、「ドメーヌ・クラレンス・ディロン」が手がけるボルドー・ワイン、「クラレンドル」。高品質、繊細でありながら、デイリーにも楽しめるワインとして欧米で名を馳せている。ナタリーは、そのワインのつくり手のリーダーであり、クラレンドルのラインナップすべてのブレンドを担当している。今回の日本滞在中、各地でクラレンドルについて、ボルドー・ワインについて、セミナーやトークイベントに参加する予定だ。「とても楽しみにしています」とナタリーは言った。彼女は言わばクラレンドルの伝道師として日本へやって来たのだ。
この夏は、ヨーロッパ全土で猛暑があった。ボルドーのブドウには、影響はあったのだろうか。
「確かに暑い時もありましたが、たまに冷え込みもあり、雨がわりと降ったので、最終的にブドウの出来は良かったんです。ただ、暑さの影響で、収穫が二週間ほど早まり、ブドウの量はいつもよりやや少なめでした」
ナタリーの仕事は、ボルドーの環境、気候と向き合うこと、ブドウの収穫に深く関わることでもある。
「収穫期は、ワインの仕事をしている中で、最も楽しい時。ブドウの生産者たち、ワイナリーで働く人々と共に過ごす、特別な日々です。一緒に畑を歩き、ブドウを味わい、収穫後にセラーで、果汁やワインを一緒に試飲する。そういったすべての時間が、かけがえのないものです。何世代にも渡り家族で働いている人たちもいて、彼らと一緒に、ブドウ畑を見渡す野外で食べる食事は、かけがえのない時間。祖父母、両親、子供たちと、三世代のファミリーが集まります」
フランスで、ワインについて語る時に必ず出てくる言葉、“テロワール”について、ナタリーに訊いてみた。
「テロワールは土地のことですが、ワインにおいて語る際には、ひと言で表現できない言葉です。テロワールはまず、その地でブドウを栽培する人のことです。つくり手の知識、経験、努力のこと。テロワールはまた、ブドウが育つ地の土壌であり、周囲の環境です。そこに生息する虫や生物、雨や太陽といった天候、温度、湿度、それらもテロワールです。さらに、ワイナリーを営む文化や歴史。そういうすべての総称が、テロワール。だからワインを飲むというのは、『大地を飲む』、ひいては『地球を飲む』ということなんです」
![ナタリー・バソ・ドウォーキン[ワインは、人と人とを結ぶもの]](https://www.switch-pub.co.jp/wp-content/uploads/2025/11/sw4312_clarendelle_05.jpg)
かつて香水業界にいたナタリーは、ワイン醸造学と品種学を学び修士号を取得、さらに国家資格も得た。一方ワインづくりの世界は、長年「男性社会」である。(香り、という共通項はあるが)まったく異なる仕事への転身、女性として、境界を越えていく勇気、チャレンジについて訊いてみた。
「日本では秘密にしないといけないことだと思いますが、私が初めてワインを飲んだのは、14歳の時。父と母がワイン好きで、夕食の席にはいつもワインがありました。ある時、1971年のビンテージの赤ワインを、父が私のグラスに注ぎました。『人生で初めてなら最高のものを味わいなさい』と両親は私に言いました。その瞬間、私のワイン愛が芽生えたんです。パリに生まれ育ち、香水業界の仕事も順調でしたが、ある時、どうしても緑が見たくなった。自然がそばにある環境に暮らしたいと感じたんです。それでワインの世界に入り、ボルドーに移住しました。当時、ワイナリーを学校に喩えるなら、30人の生徒がいて、女性は多くて5人。悔しい思いをしたこともありましたが、ワインが大好きで、良いワインをつくりたいという気持ちを失うことはなかった。女性として厳しかったか、と問われれば、昔も今も、多くの社会で男性は優位でしょう。でも今では、私のようにボーダーを越えてワインの世界で働く女性が増えました。ワインづくりのポジションにも、今は女性が大勢います」
畑から醸造、ブレンド、そして食とのマリアージュの知識や提案まで、ワインを知り尽くしたナタリーに、「あなたにとってワインとは?」という究極の質問を投げてみた。
「ワインは、人と人とを結ぶものです。そこにワインがあり、人々が良い時間を過ごす。クラレンドルのワインが、アカデミー賞授賞式のセレモニーにあり、モントルー・ジャズ・フェスティバルにもある。多くの人たちを繋ぐために存在している。ワインは大地の飲み物ですが、人と人とを結ぶ存在でもあると思います」
![ナタリー・バソ・ドウォーキン[ワインは、人と人とを結ぶもの]](https://www.switch-pub.co.jp/wp-content/uploads/2025/11/sw4312_clarendelle_06.jpg)
左からクラレンドル・ロゼ、ルージュ、ブラン。ロゼは華やかな香りと凝縮された果実の旨味が魅力。ルージュは果実とスパイスのアロマが融合した複雑な香りとなめらかな口当たりで、ブランは桃や洋ナシなどのフレッシュな香りが感じられる豊かな味わい。全国のワインショップ・エノテカ、またはエノテカ・オンラインなどで購入可能。