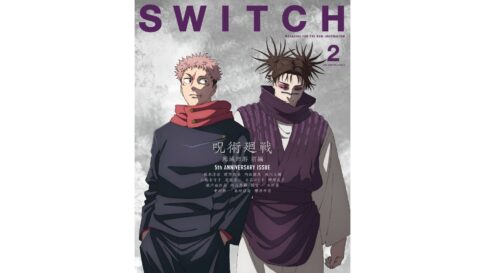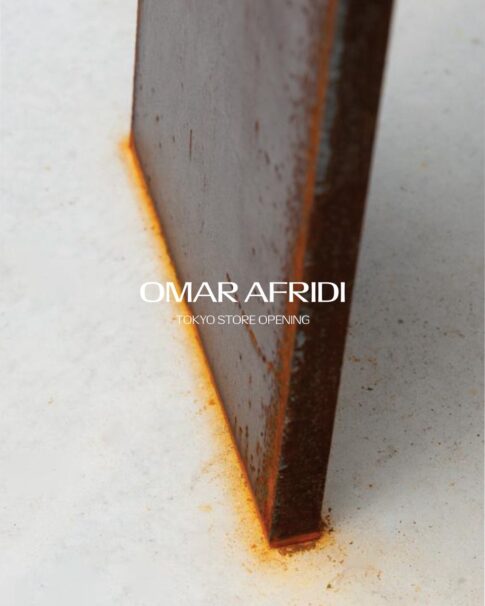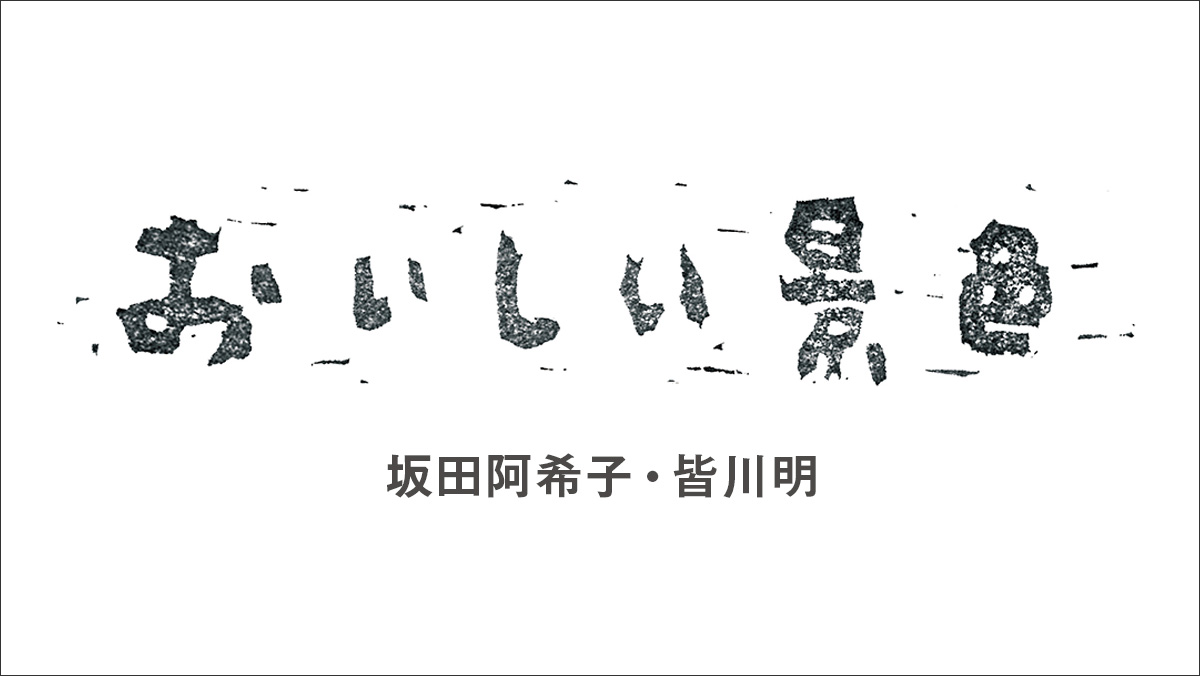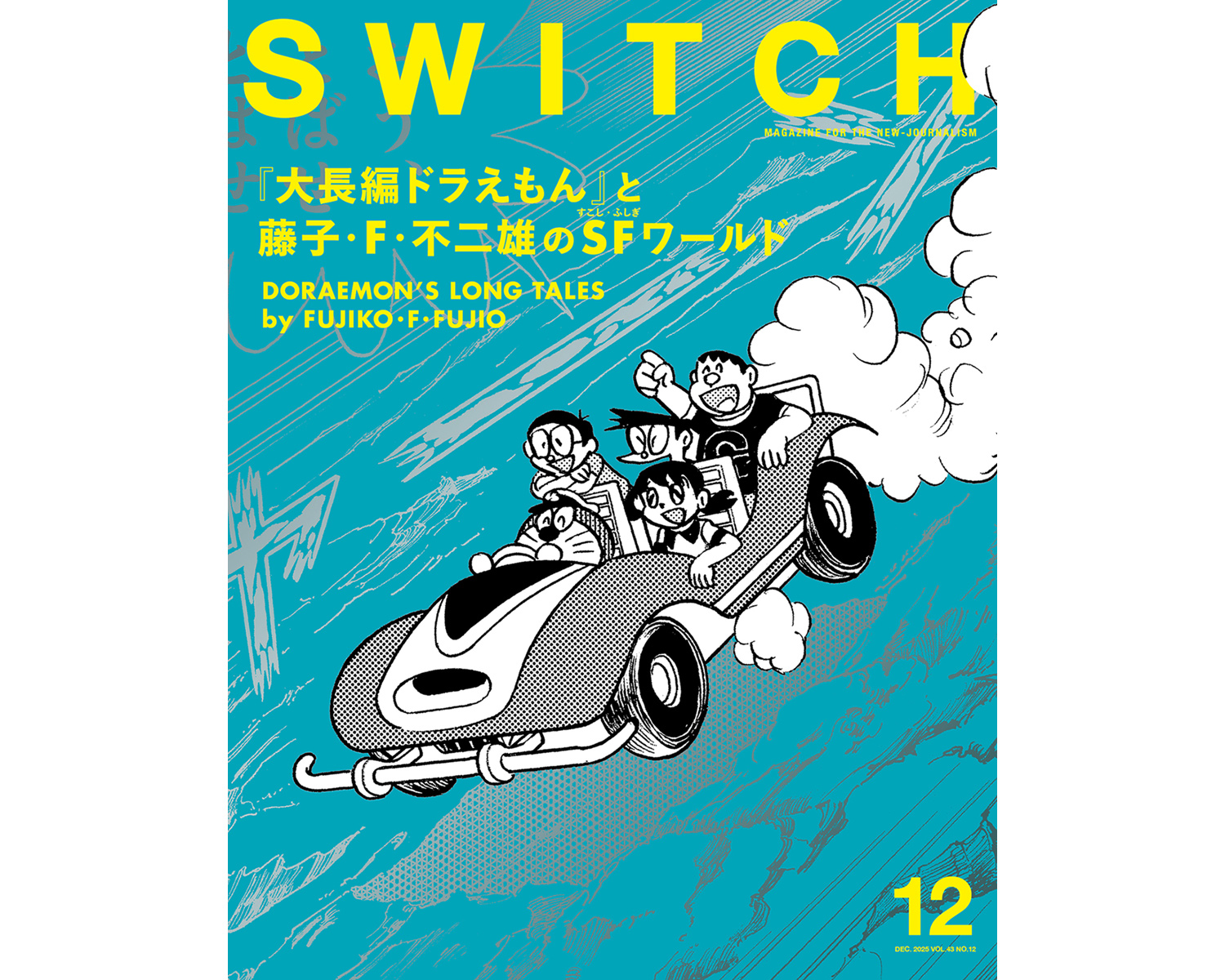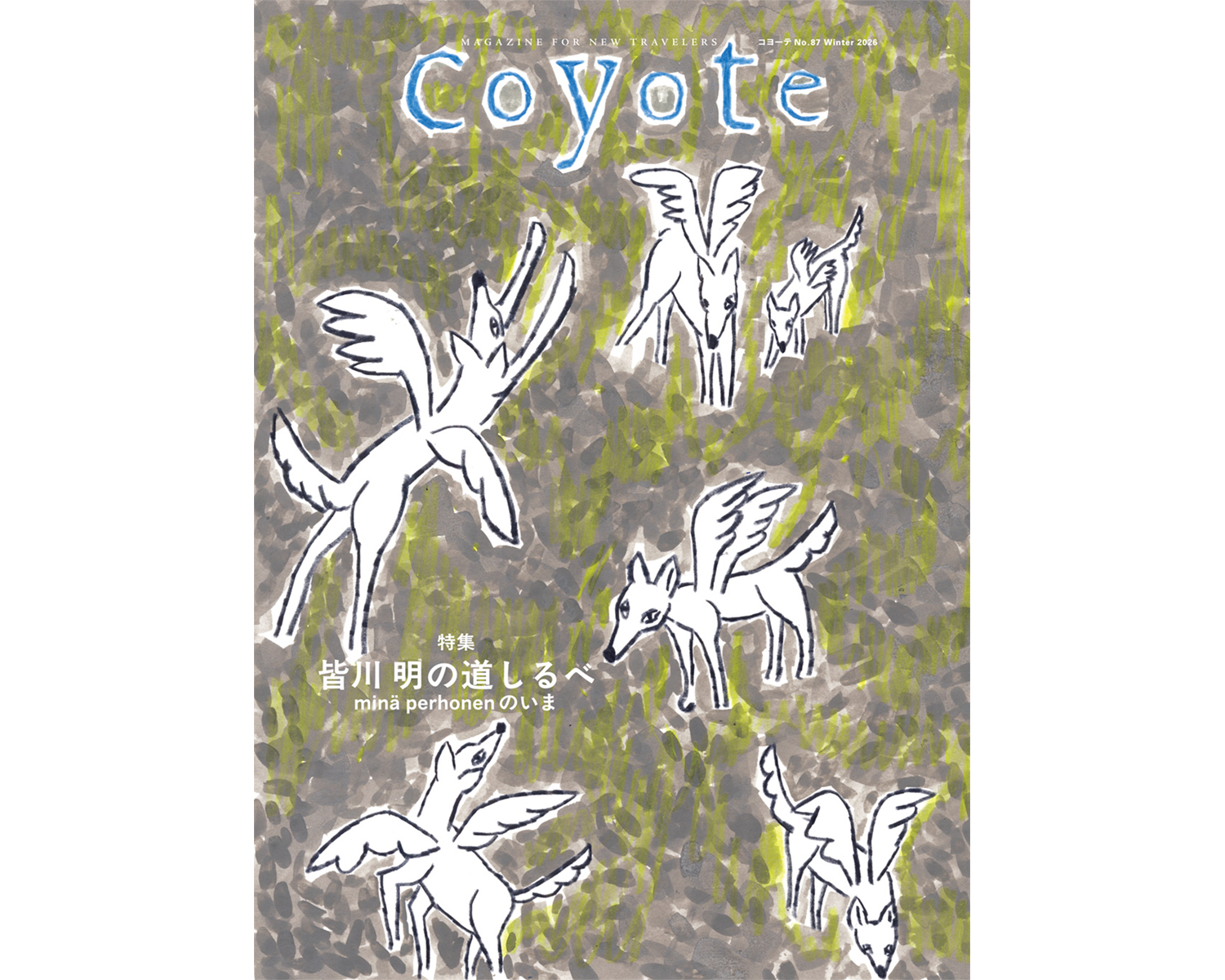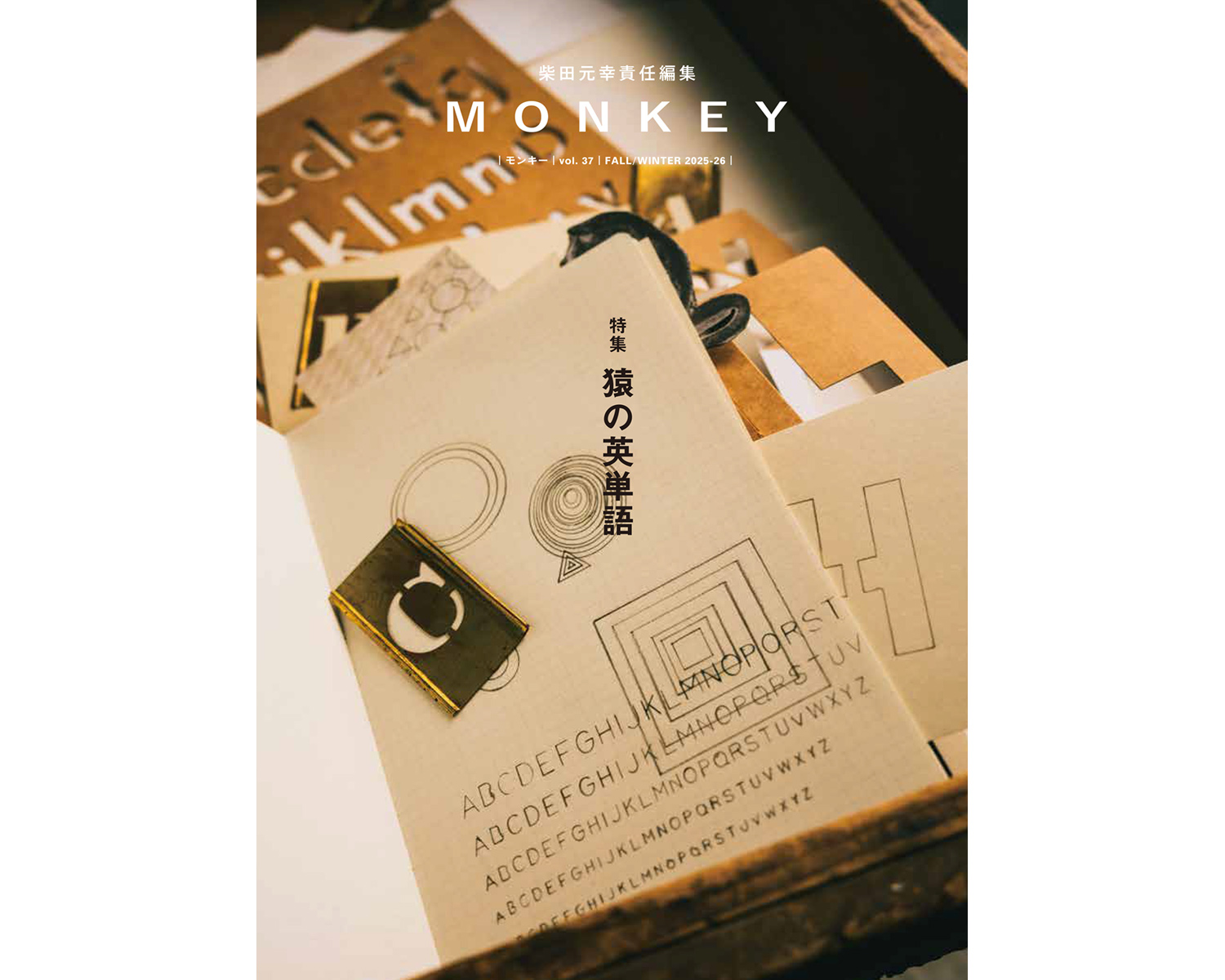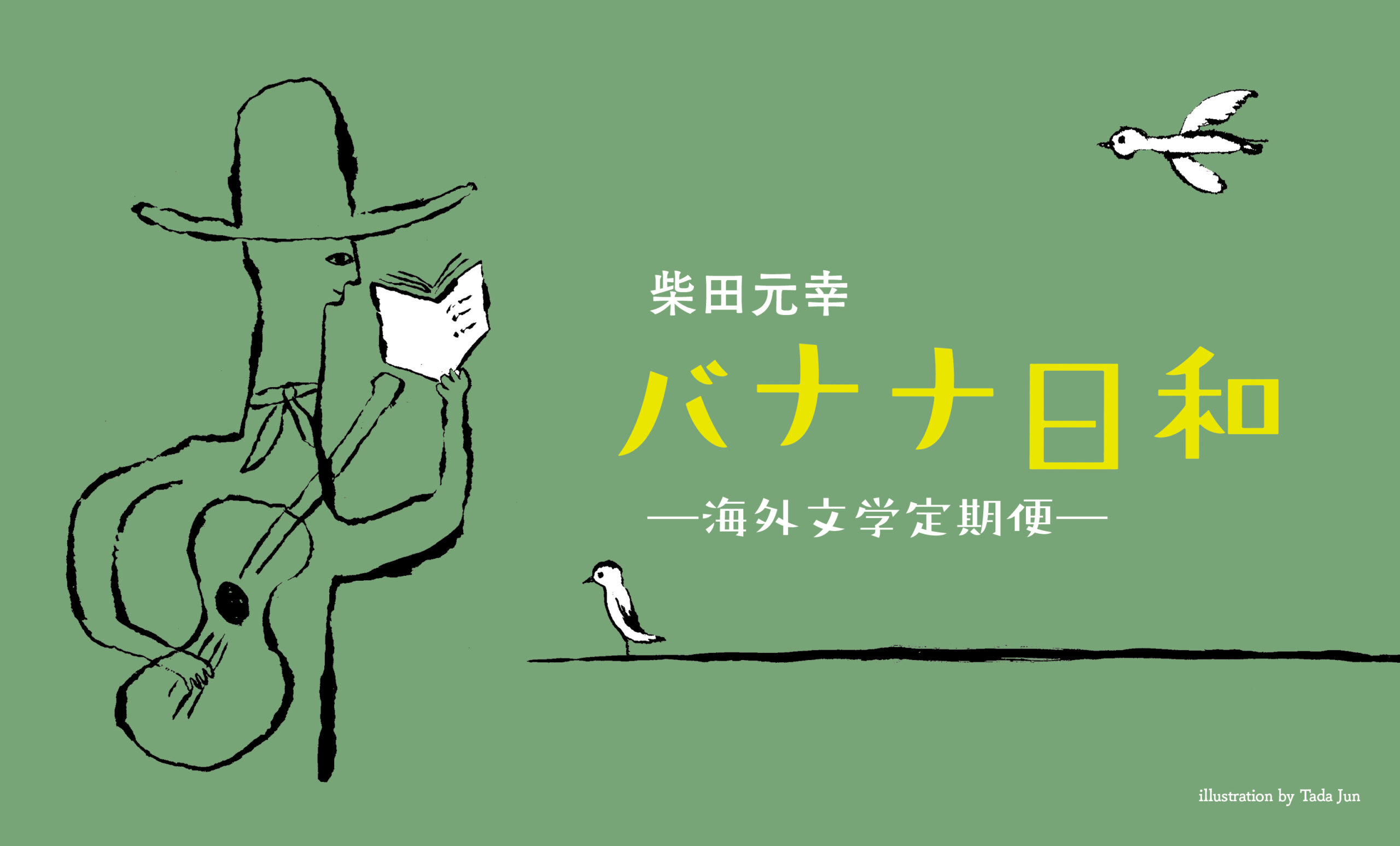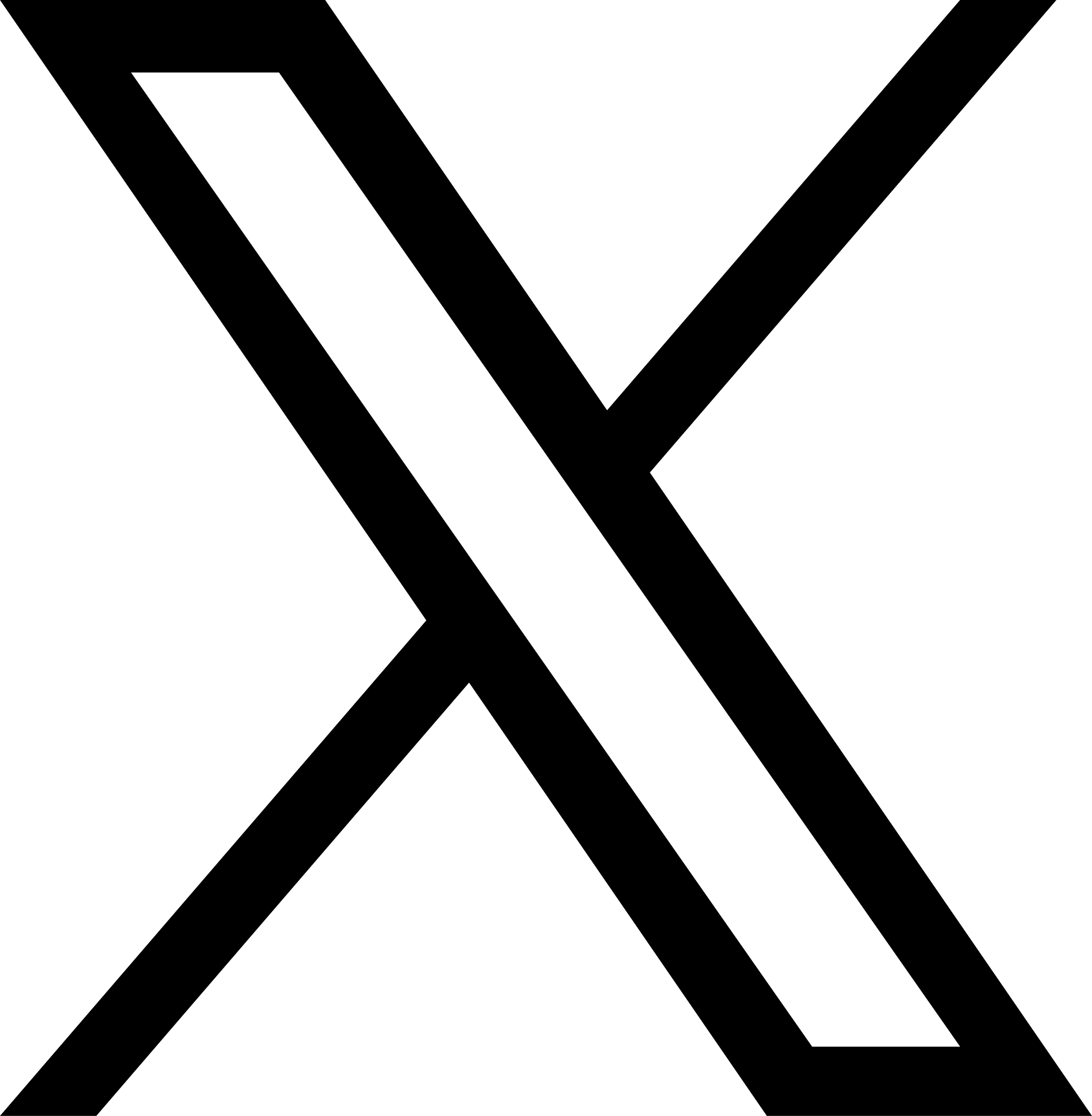Netflixシリーズ「今際の国のアリス」シーズン1~3がNetflixにて独占配信中 ©麻生羽呂・小学館/ROBOT
シーズン3の配信がついにスタートした『今際の国のアリス』。
監督を務めた佐藤信介が本作を「BRAVIA 9」で鑑賞し、感じたこととは――
佐藤が映像と音にこめた思い、そしてそれを家庭に届ける術をブラビアとともに紐解く
映像表現の極みを日常に届ける
渋谷から迷い込んだ異世界で、生き残りを賭けた「げぇむ」に挑む有栖(アリス)ら参加者たちの姿を描いたNetflixシリーズ『今際の国のアリス』。麻生羽呂の漫画を原作とする同作は、2020年のシーズン1配信開始と同時に世界的な人気を獲得し、今年九月にはシーズン3の配信が開始されたばかりだ。シリーズを通して監督を務めるのは、『キングダム』や『アイアムアヒーロー』など数々のヒット映画を手掛けてきた映画監督、佐藤信介。佐藤にとって『今際の国のアリス』は大きなチャレンジであるとともに、世界同時配信というNetflixの配信形式は、作品を作る上での心境の変化の大きなきっかけともなった。
「もちろんそれまでも、最終的には世界中の人に自分の映画を観てもらいたい、という意識はありました。しかしNetflixはそもそも多言語での世界同時配信を前提としているので、『今際の国のアリス』では企画段階から世界に向けて作っているんだという意識を持ち始めていた気がします。スタッフ一人一人に至るまで、作ったものが一瞬で地球の裏側の人にまで観られる前提で作品作りに取り組む。その姿勢は、僕の中でも大きな変化でした」
世界に届けるための大胆な仕掛け
『今際の国のアリス』を世界に届けるため、シーズン1を制作する際に佐藤は様々な仕掛けをドラマの中に織り込んだ。その仕掛けのもっとも大きなものが、シーズン1のオープニングだ。
「『今際の国のアリス』で重要なモチーフになっている“不思議の国のアリス”のような、現実世界から不思議の世界に迷い込むというのは昔からある古典的な物語のフォーマットです。しかしこの作品では、不思議の世界への入り方が重要になると考えました。結論として、どこかを通って異世界に入るわけではなく、いつもの世界から急に人が消えるという見せ方を考えたんです。消えるなら圧倒的に人がいるところ、なおかつみんなが知っている場所がいいなと考えて、渋谷の駅前から物語が始まることになりました」
人の往来が絶えない渋谷駅前。誰もいない画を撮るためには、もはや渋谷の駅前を実際に作ってしまう他に手はない、という考えに至ったという。
「実はこれまでも何度か渋谷を作ることに挑戦したこともあったんです。僕の映画には駅前で撮影したシーンが度々存在するのですが、そのうちのいくつかは、渋谷駅で撮ろうとプランを練ったものの予算などの関係で別の場所で撮ることになったものなんです。『今際の国のアリス』ではそのプランを初めて実行することができました。実際に渋谷駅前に行ってビデオコンテを作り、今はもうなくなってしまった、アリスたちが身を隠すトイレまでのルートなど、まるっと一通り渋谷駅前のセットで再現することにしました」
シーズン1から五年の歳月を経て、渋谷の街も大きな変貌を遂げた。シーズン3でもまた、渋谷は物語において重要な場所として登場する。視聴者はその変化を知っているからこそ、アリスたちの生きる世界に一層のリアリティを感じることになる。
「『今際の国のアリス』は東京という土地そのものを描いているドラマでもあると思っています。ですからシーズン1では人が忽然と消えた渋谷を描きましたし、シーズン2では荒廃した渋谷を作り上げることに腐心しました」
そのこだわりは、シーズン3でも徹底されている。佐藤は渋谷で起きるいくつかの出来事についても注目してほしいと語る。
「渋谷で始まったものは渋谷で終わるべきではないかと考えるうちに、実は渋谷ではまだげぇむをやっていないことに気づいたんです。ですから今回、最後のゲームは渋谷で行われることになります。問題はいったい何のゲームをやるのか、という部分ですね。これ以上はネタバレになってしまうので詳しくは話せませんが、最後の最後、渋谷に一体何が起こるのかという部分は、非常に力を入れて作ったシーンでもあるので、ぜひ見届けてほしいと思っています」
そういった佐藤の仕掛けは見事に大成功。『今際の国のアリス』は、配信直後から瞬く間に世界中の視聴者を熱狂させた。そしてその熱狂は、佐藤が想像もしていなかった方向にも大きな広がりを見せていく。
「僕たちが想像していたよりもずっと強く、キャラクターを視聴者の皆さんが愛してくれました。『あのキャラクターはどうなるの? 生き残るの?』という質問もたくさん受けました。日本では原作がそういった受容のされ方をしているのは知っていたのですが、世界中でも同じように広がっていったのはすごく面白かったですね。役者の皆さんはヨーロッパやアメリカに行くと、本作のキャラクターの名前で呼ばれたりもするみたいです」
蓋を開けてみれば、配信開始と同時にSNSにはたくさんのファンフィクションが流れ、視聴者は思い思いのやり方でキャラクターへの愛情を表現していった。視聴者が主体的にキャラクターに親しみ、彼らの活躍を楽しんでいる姿は、佐藤にとっても大きな刺激となった。
「もちろん僕らは当然のこととして、キャラクターを魅力的に見せることに力を注いでいます。しかしデスゲームものの『今際の国のアリス』で、それぞれのキャラクターにそこまでの愛着を感じてもらえるとは思ってもみなかったんです。過酷で複雑に展開する映像の中で、実はキャラクターたちの生き様や人間性の描写が作品においての生命線だったと気づかされました。どんなジャンルの作品であっても、最終的には人間の在り方や本質に帰っていくようなストーリーを、僕たちはずっと作っていたんです。渋谷の駅前から人がいなくなるという大きな仕掛けに驚くのもすごく大事だけど、やっぱり最後は人間ドラマに誰もが惹かれていくということを、世界中の視聴者たちと共有することができました。
世界中で、映画祭などの特別な場ではなく街に暮らす人たちの日常の中で観てもらえている。老若男女問わず『今際の国のアリス』のことを知ってくれている。そのことが何よりも嬉しいことでした」

Mini LEDバックライト搭載テレビ「BRAVIA 9」(www.sony.jp/bravia/special/bravia9_XR90)
サウンドバー「BRAVIA Theatre Bar 9」/オプションスピーカー「SA-SW5/SA-RS5」(www.sony.jp/home-theater)
ブラビアでの見え方をリファレンスに
世界中のあらゆる国で、いつでも自分たちの好きな場所やタイミングで観ることのできる配信作品は、視聴者の属性も多様なら、その視聴環境も千差万別だ。佐藤は、細かな部分までこだわり抜いて完成させた映像を最高の環境で観てほしいという願いは抱きつつも、リビングのテレビや手の中のスマホで作品を鑑賞する視聴者の姿は、常に念頭にあると語る。実は、今回の『今際の国のアリス』制作過程において、ソニーのテレビ「ブラビア」が活躍したと佐藤は振り返る。
「配信ドラマの最終的な調整作業にはマスターモニター(色彩や解像度の確認のためのモニター)での見え方を確認するのが常ですが、それと同時に僕たちのラボではブラビアでの見え方を最終確認と調整に使っているんです。実はそれは劇場公開の映画も同じです。スクリーンでの見え方を確認しながら、最終的にはその作品もパッケージやデジタル配信など、ご家庭のテレビで視聴していただくことになりますから、僕らの頭の中には“やっぱり最後はテレビだ”という思いがあるんです」
今回佐藤にはMini LEDバックライトを搭載した最新モデル「BRAVIA 9」で『今際の国のアリス』シーズン3を視聴してもらった。シーズン3にも数々のげぇむが登場するが、その中でもとあるクイズの場面に佐藤は感嘆の声を漏らした。真夜中の境内で開催されるクイズの誤答の代償として、参加者たちに無数の火矢が降り注ぐシーンだ。日頃から映像制作にブラビアを採用している佐藤の目に、最新技術を搭載したBRAVIA 9の映像はどのように映ったのか。
「色や光の再現性が素晴らしいですね。このシーンでは、火で照らされている部分と夜の闇の暗さの部分に気を使いつつ、炎で照り返される人の肌の質感や雰囲気を表現したいと思っていました。火自体の風合いから人物への反射まで上手く表現できるよう、黒も含めた色のバランスを一つ一つ細かく調整しています。さらに、あたりを舞う火の粉の細かさや美しさにもこだわって、何度もかなり入念にチェックしています。BRAVIA 9では、そういった微細な表現が漏れなく画面に浮き出ていて、非常に驚きました」
佐藤が手掛けてきた作品の多くは、迫力と驚きに満ちたダイナミックな画面作りが強く印象に残る。しかし、それと同時に繊細な表現を丁寧に描写することで生まれる落差こそを、佐藤は重視しているという。
「今日、BRAVIA 9でシーズン3のいくつかの場面を観させていただいて、僕らが表現したい繊細さ、細かい表現を最新の技術ですくい取っていただいていることを実感することができました。今の時代は皆さんいろんな視聴環境で作品をご覧になっているので、すべての人に作った画面をありのままに観ていただくことはやはり難しいことです。なのですが、今回BRAVIA 9の映像描写力を体験して、こだわって仕上げたものがそのまま表現されていることを実感すると、クリエイターとして非常に勇気づけられますね」
加えて、佐藤はBRAVIA 9に採用されたMini LEDバックライトが実現する「黒」の表現力にも注目する。
「黒の落ち方は本当にすごいですよね。黒は映像作品にとっては非常に重要な色です。映画を作る際には、どうしても僕らは黒い部分に対して光を当てて色を持ち上げ、きちんと細部も見えるようにしたくなりがちです。しかし時には本当に真っ黒でいい場面もあるのではないかと常々思っていて、僕らはそういう混じりっけなしの黒を“勇気ある黒”と呼んでいるんです。ラボで使っているブラビアの表現を観た時に、僕らはこの勇気ある黒を家庭に持ち込むことができるんだと背中を押されながら制作していました」
劇場に劣らぬサウンドバーの音表現
佐藤のこだわりは映像だけにはとどまらず、音に関しても胃が痛くなるほどの情熱と労力を注いでいるという。今回佐藤には、テレビだけでなく「BRAVIA Theatre Bar 9」やサブウーファーなど、ブラビアと連携することで映画館にいるような立体的な音響を実現するサウンドシステムも一緒に体験してもらった。
「映像体験において聴感はとても大切です。なので、劇場公開作品の音のレンジと配信作品の音のレンジはそもそもが違うのですが、配信作品でも劇場に近い体験をしてもらうため、技術的な部分だけではなく感情的な面からのアプローチも含めて様々な工夫をしています。今日のサウンドバーではそういった音へのこだわりがちゃんと表現されていて、僕たち作り手の意図した音で作品を視聴してくれている人がいるんだと思えたことは、大きな励みになります。劇場とはまた違った、先進性のある新しい感動が発展するかもしれないとも思いました」
ソニーが開発してきた最新の技術を投入し、視聴者に制作陣がこだわり抜いた映像表現をありのままに届けるブラビア。映画『キングダム』の撮影などでソニー製のカメラを使う佐藤にとっては、ソニーという会社の在り方もまた、特別な意味を持つものだ。
「映画作りは本当にわけのわからない世界です。大成功したと思ったら次はコテンパンに失敗したり、すごい作品を作れたと思ってもまったく評価されないなんてこともいくらでもあります。でも実はソニーは会社としてそういう泥臭い映画作りをずっと続けているんですよね。あらゆる方面から映像作品業界を盛り上げ続け、より多くの人の元へたくさんの作品を届けていく。それは世界的にも類を見ない営みです。ソニーにはこれからもその道を極めていってほしいですね」
佐藤信介 1970年、広島県生まれ。学生時代の自主制作映画『寮内厳粛』がぴあフィルムフェスティバル94でグランプリを受賞。Netflixシリーズ「今際の国のアリス」シーズン1~3で監督・脚本を手掛ける
TEXT: YAMADA SHUKA
STYLING: DAN
HAIR & MAKE-UP: NAKAYAMA MEGUMI
[衣装]シャツ、カーディガン/junhashimoto(ジュンハシモト 表参道ヒルズ:03-5414-1400)、スラックス/PRIVE~designsuit~(PRIVE~designsuit~表参道店:070-1591-9560)